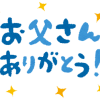3月3日と言えば、ひな祭りですね。
子どもから「どうしておひな様を飾るの?」と無邪気に質問されて、
困ってしまったことはありませんか?
意外と本来の由来や意味などがわからないことも多いです。
気になる桃の節句に関してまとめてみました。
桃の節句の由来とは?
その期限は古代中国にまでさかのぼります。
中国三国時代の魏において、
河で禊を行ったあとに宴会を行う「上巳の節句」という習慣がありました。
上巳とは3月上旬の巳の日を意味します。
これが、平安時代に日本に伝えられ、
日本では人間の代わりに人形を流す「流し雛」と呼ばれる形に発展しました。
さらに貴族の子どもの間で、現代のおままごとにあたる「ひいな遊び」、
いわゆる人形遊びが行われるようになります。
これが、ひな祭りの原型です。
「流し雛」の風習と「ひいな遊び」が融合し、
やがては流すものから飾るものへと変わり、
その後江戸幕府によって3月3日を「桃の節句」として定着しました。
女の子の健やかで幸せな成長を願うという
美しい思いやりがある行事です。
なぜ桃の節句と名付けられたかというと、
邪気祓いのために、
上巳の節句に桃の木を魔除けとして飾ったためと言われています。
また旧暦の3月3日が、
ちょうど桃の花が咲く頃だったからではないかという説もあるようです。
現代の桃の節句の意味とは?
もともとがいろいろな風習が混ざり合って生まれた行事の為、
込められている意味は一つではありません。
現代においては、特に女の子の健康と幸福をお祈りして祝うという
意味がある行事として楽しまれています。
ひな人形には見た目に華やかなだけでなく、
女の子に代わって災厄を引き受けてくれる存在としての
意味合いも込められているのです。
地域によっては、お祝いとしてひな人形を贈る風習があるところもあります。
人形を飾るようになったのは江戸時代ですが、
三人官女や五人囃子などを加えた段飾りが
一般的になったのは明治時代と比較的近年になってからです。
桃の節句に用意する縁起のいい食べ物は何?
主に以下の5つがあげられます。
| 1:はまぐりの吸い物
2:菱餅(ひしもち) 3:ひなあられ 4:白酒 5:ちらし寿司 |
順番に見ていきましょう。
1:はまぐりの吸い物
はまぐりは対になった貝どうしでないと
絶対に合わないと言われています。
そのため、「一生涯一人の相手と添い遂げる」という
理想的な夫婦像の象徴として親しまれてきました。
女の子が、将来素敵な男性と添い遂げられるように
という意味合いが込められています。
現在はまぐりが高価なため、あさりで代用することもあります。
2:菱餅(ひしもち)
色にそれぞれ意味があり、
緑は「健康と長寿」白は「洗浄」ピンクは「魔除け」を表すとされています。
また、緑は「大地」白は「雪」ピンクは「桃の花」を表すことから、
「雪がとけて大地に草が芽生き桃の花が咲く」
という意味が込められているという説もあります。
いずれにしろ、女の子の健やかな成長が願われています。
3:ひなあられ
カラフルなひなあられには、ピンク・緑・黄・白の4色があり、
それぞれ四季を表しているとされています。
女の子が1年中幸せでいられるようにとの意味が込められているのです。
4:白酒
もともとは桃の花びらを漬けた「桃花酒」が飲まれていたようです。
桃が邪気をはらうことから、気力が充実するとされています。
現代では白酒が一般的です。
子どもにはノンアルコールの甘酒が振舞われます。
5:ちらし寿司
ちらし寿司のポイントは具材の意味です。
レンコンは見通しがきく、豆が健康でマメに働ける、
エビが長寿などそれぞれ縁起のいい具が用いられています。
また、大人数の食卓をにぎわかせてくれるという
実用的な観点からも喜ばれている存在です。
見た目に華やかなだけでなく、
全て女の子の幸せな一生を願う縁起の良い意味がそれぞれ込められており、
全て用意することが望ましいとされているのです。
家族が揃って宴会を楽しむという目的もありますが、
神仏に捧げる品という意味もありますので、
最低でも上記の5つは用意しておくことがおすすめできます。
女の子と一緒に用意をすることで、
自然と伝統を伝えるという役割も果たすことができるでしょう。
1000年以上の歴史がある日本の素敵な伝統行事ですので、
次の世代に伝えることも大切ですね。
地域によっては、その地方ならではの和菓子などが
振舞われることもあります。
有名なのは京都の「ひちぎり」「ひちきり」という生菓子でしょう。
ちなみに京都はひな人形の位置も逆です。
一般的には結婚式の新郎新婦の並び方と同じく
左が男雛・右が女雛ですが、京都は右が男雛・左が女雛という位置に飾ります。
御所の伝統にならったものであると言われています。
最後に
女の子の幸せを願う由緒正しい行事が桃の節句です。
伝統にそって、楽しんでお祝いしてあげましょう。
スポンサーリンク