
1年の中でももっとも寒い時期に出す寒中見舞い。
最近では、喪中の方に年賀状の代わり出したり、うっかり年賀状の時期を過ぎてしまった時にも活用されることがあります。
でも、いざ書こうとすると文章が思い浮かばなくて困ってしまうことも・・・。
今回は、寒中見舞いの例文をご紹介します。友人に送る時などに活用してみてくださいね。
寒中見舞いとは?

寒さがもっとも厳しい時期に送る季節の便りの一つです。
寒中見舞いの時期は、体調を崩す人も多く家にこもりがちな頃なので、
手紙やはがきを使って相手を気遣ったり、自分の近況などを伝えることに役立てます。
「寒くてなかなか会いに行けないけどどうしているかなぁ・・・」と気になっている時に、
手紙やはがきが来るとなんとなく嬉しいものです。
近年では、喪中の方に年賀状の代わりとして活用したり、
年賀状の時期を過ぎてしまった時に年賀状の代わりの挨拶状として使うこともあります。
手紙とはがき両方の形式があり、自分の好みに合わせて選ぶことが可能です。
寒中見舞い用に、イラストや写真で加工された専用の便箋やはがきが売られています。
どれを使おうか選ぶ過程も楽しいでしょう。
寒中見舞いの例文

寒中見舞いの基本形式はこちらです。
|
①寒中見舞いの挨拶となる言葉 ②先方の安否をたずねる言葉 ③書き手の近況報告(お礼など書くこともあります) ④相手の体調を気づかう言葉 ⑤日付 |
では、例文を見ていきましょう。
基本的な寒中見舞いの例
寒中お見舞い申し上げます
本格的な寒さを迎えておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
おかげさまで私どもは元気に暮らしておりますので、ご安心ください。
時期柄、どうぞお風邪など召しませぬよう、ご自愛ください。
平成◯◯年 一月
お礼を伝える寒中見舞いの例
寒中お見舞い申し上げます
寒さ厳しい折、ご家族の皆様におかれましてはますますご健勝のこととお喜び申し上げます。
昨年はお世話になり、ありがとうございました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
余寒も厳しいようですが、皆様のご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。
平成◯◯年 一月
寒中見舞いを友人に出す時は?

友人に出す時は、少し砕けた言い回しをしても良いでしょう。
友人に寒中見舞いを出す場合の例
寒中お見舞い申し上げます
寒さ厳しい折、いかがお過ごしでしょうか。
まだまだ寒さが続きそうですが、お体を大切にお過ごしください。
(ここに、自分の近況や相手に合わせた親しみのある文章を添える)
平成◯◯年 一月
親しい友人の場合は、よりオリジナリティーの高い文面にした方が喜んでもらえる確率が高まると言えます。
ただし、相手との距離感にもよりますので、不安なら無難な文面で出したほうが良いかもしれません。
手紙を出して気にかけてくれたという事実だけでも喜んでもらえる場合もあります。
寒中見舞いを出す時期は?

寒中見舞いは、寒中に届くように出すことが基本です。
寒中とは、『小寒』と『大寒』の期間を指しています。
小寒は1月5日頃、大寒は1月20日頃です。
ただし、1月5日頃はまだ年賀状のやり取りをしている時期なので、
一般的には、1月8日以降から寒中見舞いを出し始めます。
終わりに関しては、立春の前日である節分の2月3日までは、
寒中見舞いを出す方が多いと言われています。
よって時期としては、1月8日~2月3日までに出すのが正当と言えるでしょう。
ちなみに、2月5日以降になら余寒見舞いとなります。
寒中見舞いを出す時の注意点
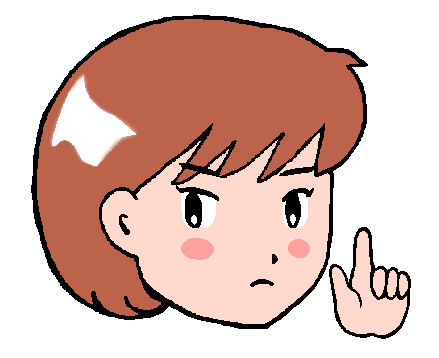
注意点は主に2つです。
まず、相手が喪中の時には、おめでたい言葉を避けることが必須となります。
お悔やみの気持ちなどを伝えたい時は、寒中見舞いの時期を待たずに、
封書の形式で気持ちを伝えるという方法もあります。心を込めて作成しましょう。
余った年賀状を利用することは失礼なのでやめましょう。
寒中見舞い用のはがきをキチンと買って作成することが大切です。
もちろん「出し忘れた」や「書き忘れた」という表現も失礼なので使ってはいけません。
全ての手紙の基本ですが、相手を思いやる気持ちが必要と言えるでしょう。
受け取った相手がイヤな気持ちになってしまうようなものは避けたいですね。
相手のことを考えて言葉の使い方などに細心の注意を払い作成することが肝心です。
あなたの手紙に込めた気持ちは、受け取った相手に届きます。
良い関係が続いていくような寒中見舞いを送るようにしましょう。
寒中見舞いの例文!友人に送るなら?まとめ
寒中見舞いは、1年で一番最初に出す手紙やはがきになることもあります。
寒い時期は人恋しくなる人も多いですから、もらうと嬉しいと感じる人も多いでしょう。
基本的に形式にそって作成し、友人に出す場合はより親しみを込めた文章を添える方法がオススメと言えます。
出す時期や注意点に気をつけましょう。
相手のことを思いやり、最適の方法で出すことがポイントです。
スポンサーリンク











