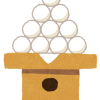1年の中でも特に美しい月が見られるのが中秋の名月です。
子供の頃からお月見の習慣に親しんでいる方も多いでしょう。
日本では古くからお月見が行われていますが
由来をご存でしょうか?
また世界ではどんな慣習があるのでしょうか?
今回は由来などと合わせて世界の中秋の名月の様子をご紹介します。
また、中秋の名月と十五夜の違いなどについてもまとめてみました。
これを読めば秋の夜長を存分に味わうことができるでしょう。
中秋の名月とは?なぜ秋にお月見をするの?
旧暦の8月15日の夕方に現れる月を中秋の名月と呼びます。
「中秋」と書くように秋の真ん中の満月を意味していますが
実は必ずしも満月が見られるとは限りません。
8月15日は、秋である7月~9月のちょうど真ん中の日にあたります。
その為キリが良いのですが、新月から満月になるには約14.8日かかり
月の軌道が楕円形であるため、15日が満月になるとは言えないのです。
ただし、15日は平均的に満月が見られることが多いとされています。
月には、立待月、居待月、寝待月などの別名が豊富なように
昔から人々は満月に固執して愛でるよりも、月そのものを見ること
を楽しんできました。
中秋の名月は満月でない年もありますが、それでも美しいことに
変わりはなく、人々は秋の真ん中である日の美しい月夜を
堪能してきたと言えるでしょう。
月の高さは夏に低くなり、冬に高くなります。
お月見をするのにちょうど良い高さになるのが、春か秋です。
お月見は1年を通していつでも行なえますが、特に月夜の美しさを
味わえるのが秋であることから、秋にお月見をする習慣が根付いた
と言われています。
「春に三日の晴れ無し」ということわざもある通り、春は雨が多いです。
その為、月がちょうど良い高さにあっても、地上からは見えないので
気づかれません。
その点、秋は「天高く馬肥ゆる秋」とも言われるほど、澄み切った
美しい空を見ることができます。
ふと見上げた時に美しい月夜の美しさにハッとする機会は秋のほうが
断然多いと言えるでしょう。
秋のお月見が広く一般に親しまれるようになったのも納得です。
中秋の名月と仲秋の名月は違う?
読みは同じ「ちゅうしゅうのめいげつ」でありながら
「中秋の名月」と「仲秋の名月」という2つの書き方が存在します。
結論から言うと、どちらを書いても正解です。
しかし、使われている漢字によって意味合いが異なります。
旧暦では秋は7~9月の3ヶ月であり、7月を初秋、8月を仲秋
9月を晩秋を称します。
つまり仲秋とは8月の別称です。
仲秋の名月とは、8月の名月のことを指します。
中秋の名月はご紹介したとおり旧暦の8月15日の夕方に
現れる月のことです。
仲秋の名月は範囲が広いですが、中秋の名月はピンポイントを
指しています。
意味合いを正しく理解して使い分けるようにしましょう。
中秋の名月にお月見をする由来

中国から文化を吸収していた平安時代の書物には
延喜9年(909年)に醍醐天皇が月見の宴を執り行ったという
記録が残されています。
これが日本において最も古いお月見の記録です。
中秋の名月を愛でるようになった背景には、中国の「望月」という
月を見る催しを貴族が真似、その後民間に定着するようになったの
ではないかと言われています。
また、秋という時期は、ちょうど作物の収穫を終え
その年の恵みに感謝する時です。
お月見が民間に定着するようになった背景には、秋の収穫を天に
感謝する「収穫祭」の慣習と融合したことも大きいでしょう。
現在では幸せや健康を願う目的でお月見が行われています。
世界の中秋の名月にはどんなものがあるの?
日本人にもなじみ深いお月見ですが、世界ではどのように
祝われているのでしょうか?代表的な国々の習慣をご紹介します。
●中国
日本のお月見のもととなったのが中国の慣習だった事からも
わかるとおり、中国は古代からお月見を楽しむ国でした。
現在でもその慣習は残っており、旧暦の8月15日には「仲秋節」
と呼ばれる一大行事が開催されます。
「仲秋節」は、今や世界的に有名になった中国で最も大きな行事
である「春節(旧正月)」と並び、非常に盛大な行事です。
「中国の四大伝統祭り」の一つに数えられています。
中国の人は、仲秋節の時期に各地から家に帰り、家族で月餅を
食べながらお月見を楽しみます。
かつては祭祀行事としての側面が大きかったですが
今日では娯楽として受け入れられており、美しい月夜を家族で
過ごす行事として親しまれています。
各地によって習慣が異なる場合もありますが、中でも有名なのは
提灯や灯籠を鑑賞する活動です。
闇夜に浮かび上がる灯籠の灯りには独特の趣があり、月見と
合わせて人々の目を楽しませています。
●韓国
お隣の国・韓国でも、旧暦の8月15日は重要な日とされています。
「秋夕」と呼ばれ韓国3大行事の一つと呼ばれる大きな名節に
あたります。
その為旧暦の8月15日とその前後、計3日間が祝日となります。
中国と同じく、韓国の人々はこの日に親族を訪問し
茶礼(チャレ)などを行います。
秋夕は、日本の中秋の名月というより、中国の仲秋節に近いと
言えるでしょう。
お月見はタルマジと呼ばれ、秋夕に行われてきた風習の一つ
として知られています。
この日の月で1年の吉凶を占ったり、高台からの月見を楽しむ
などが行われているのです。
●香港
香港でも仲秋節があり、月餅を食べ月を愛でることが一般的です。
日本だと月餅と言えばオーソドックスな形式の商品を見かける
程度ですが、香港の月餅は年々進化しており、非常にバラエティー
豊かであることで知られています。
ヘルシー志向やチョコレート月餅など、他にはないユニークな
月餅も取り揃えられています。
山頂や高台などの高い場所に提灯の灯りを頼りに家族で出向いて
月を愛でながらお気に入りの月餅を食べるという慣習が現在でも
行われているのです。
●台湾
台湾も旧暦の8月15日は仲秋節なので、大切なお祝いの日と
認識されています。
大晦日と並んで、ポピュラーなお祝いの日であり、月餅と大きな
柚子を食べることが基本です。
台湾人も家族を大切にしており、アットホームな印象が強いと
言えます。
ユニークなのが、バーベキューをしながらお月見をする習慣が
あることです。
家族でバーベキューを行い、最後に月餅と大きな柚子のおやつを
楽しむのが台湾流のお月見とされています。
ちなみに、お月見の際にお月様を指で指す行為は大変罰当たりと
されています。
もし指で指してしまうと耳に怪我をすると伝えられているのです。
台湾にもお月様にちなんだ伝説があり、愛でると同時に
畏怖の対象でもあったことがわかります。
●ベトナム
中国の中秋節が伝えられ、その伝統が受け継がれました。
現地では 「Tết Trung thu(テットチュントゥ=節中秋)」
と呼ばれています。もともとは中国や日本と同じくお月見を行う
風習がありましたが、現在では子どもの為の日として定着しています。
言わば子どものお祭りであり、日頃買ってもらえないおもちゃを
ねだっても許されることから、この日を楽しみにしている
子どもも多いです。
日本のクリスマスをイメージするとわかりやすいかもしれません。
現在では月を愛でるという慣習は少なくなりましたが
子ども達の笑顔があふれる日としてベトナムの人に親しまれています。
なお、月餅を食べる習慣は現在でも残っており、多種多様な月餅が
販売されています。
●ヨーロッパ
日本をはじめアジア圏では、お月様を神聖なものと考え
お月見という独特の慣習が古くから親しまれてきました。
しかし、意外なことに多くの国ではお月様を不吉なものとして
恐れられてきた歴史があります。
ヨーロッパでは古くから月の狂気が語られており、お月見をして
愛でるという習慣はありません。
有名な狼男の伝説からもわかるとおり、月の光は情緒があるというより
人を狂わせる怖いものと認識されていたようです。
シェイクスピアの作品の中にも
「月の軌道が狂っていつもより近づいたから人間どもが狂いだしたのさ」
というセリフが登場します。
ヨーロッパの人からすると、月は不吉なシンボルとされてきたと
言えるでしょう。
中秋の名月と十五夜の違いとは?

秋になると「中秋の名月だからお月見をしよう」という言葉も
聞かれますが、同時に「十五夜だからお月見をしよう」という
声も聞こえます。
中秋の名月と十五夜の違いは何でしょうか?
正確に言うと、十五夜と中秋の名月は同じ日を指します。
十五夜は、新月から数えて15日めの夜であり
月の満ち欠けが繰り返されるように1年の内に何度も
おとずれます。
その十五夜のうちで、特に秋の旧暦8月15日の月を
中秋の名月と呼ぶのです。
秋の収穫を祝って月を見ながら月見団子を食べる風習が
現代では家族の健康と幸福の願いを込めてお月見をした後
飾ってあった月見団子を食べる風習への変わっています。
秋の夜長に美しい月夜を愛でつつ家族で過ごす時間は
最高の贅沢なのかもしれませんね。
中秋の名月や十五夜で見える月にはうさぎがいる?世界では?

実は月は地球よりも早く誕生しており、約44億歳と言われています。
月は自転と公転が同じ27.32日である関係で、地球から裏側を
見ることができません。私たちは常に月の表側を見ていることになります。
角度は異なりますが、各国で同じ模様を見ているわけです。
日本では月の模様を「月のうさぎが餅つきしている姿」と
見たてることが一般的です。
望遠鏡のなかった時代、人々は肉眼を頼りに、月の模様に
独自の解釈を加え様々な物語を生み出しました。
各国では、どのように見えているのでしょうか?
| 中国:不老不死の薬を作っているうさぎ |
| 韓国:うさぎの餅つき |
| アメリカ:女性の横顔 |
| カナダ:バケツを運ぶ女性 |
| 北ヨーロッパ:水をかつぐ男女 |
| 南ヨーロッパ:カニ |
| 東ヨーロッパ:女性の横顔 |
| ドイツ:薪をかつぐ男 |
| アラビア:ほえているライオン |
中国や韓国は日本と同じくうさぎとみなしているようですね。
各国によって見えているものには違いがあるようです。
特に印象的なのは、アラブの「吠えているライオン」でしょう。
このライオンは、尻尾まである形とされています。
実はこのしっぽの部分は「危険の海」と呼ばれる部分であり
肉眼で見ることは難しいとされています。
アラブ人は目が良かったので、しっぽの部分まで
見分けられたのでしょう。
他にも、オランダでは「悪行の報いとして幽閉された男の姿」と
されているなど、月の模様に対して国によって抱くイメージは
変わっています。
各国を訪れた時に月を見上げて確かめてみるのも面白いでしょう。
中秋の名月・十五夜以外にもお月見をする?
お月見と言えば中秋の名月・十五夜が有名ですが
実はそれ以外にもお月見をする伝統があります。
「十三夜」と「十日夜」です。
十三夜は、旧暦9月13日のお月見のことであり
ちょうど十五夜の一ヶ月後にあたります。
十五夜か十三夜どちらか一方しかお月見しないことは
「片月見」「片見月」と呼ばれ縁起が悪いとされています。
ちなみに、十三夜は日本独特の慣習です。
十五夜の発祥である中国には、十三夜という慣習はありません。
十三夜は十五夜と同じくお月見を楽しみます。
栗や豆の収穫をお祝いする目的もあるので
「栗名月」や「豆名月」という別名も存在しています。
十日夜は旧暦10月10日に行われる収穫祭のことです。
こちらはお月見がメインではありません。
収穫を祝うお祭りがメインであり、各地で風習は異なります。
主に東日本で盛んな行事ですが、西日本にも「亥の子」と呼ばれる
類似した行事があります。
十五夜、十三夜、十日夜は晴れの日が多く、お月見できることから
縁起が良いとされています。
中秋の名月・十五夜などでお月見をする方法
こちらでは代表的なお月見のやり方をご紹介します。
お月見には主に3つのお供え物をします。「
月見団子」「ススキ」「収穫した野菜や果物」です。
それぞれに意味があります。
●月見団子
満月を同じくまんまるな形をしていることから、物事が結実すると
いう意味合いを持っています。
収穫を祝い米の粉を団子の形にして供えたことが始まりと
されており、現代では健康と幸福の象徴して親しまれています。
基本的には15個お供えしますが、1年を表す12個(うるう年には13個)
や、簡略化した5個を供える場合もあります。
また最近ではバリエーションに富んでおり、月見団子ではなく
まんじゅうを供えたりする地域もあります。
月見団子と言えば白い丸い形を想像する方が多いかもしれませんが
地域によって違いがあります。
白い団子タイプでも、中に何もないっていないプレーンタイプと
中にあんこなどが入っているタイプに分かれており
一般的に中にあんこなどが入っているもののほうがやや大きいです。
中国・四国地方では単体ではなく串団子タイプの月見団子が存在します。
愛知県名古屋市にはしずく型タイプの細長い形の月見団子があり
静岡県はへそ餅型とユニークです。
その地域に根ざした月見団子を楽しむことも一興でしょう。
●ススキ
ススキは月の神様の依り代と考えられています。
本来は稲穂を依り代とするのですが、中秋の名月の時期には稲穂が
ないことから、形が似ているススキを依り代とした経緯があります。
ススキにはもともと魔除けの意味があることから
お月見の後には軒先に吊るし家を守ってもらうという
風習も伝えられています。
ススキは田舎であれば自生しているものを採ることもできますが
自分の土地でない場合、所有者がいることから迂闊に採れないでしょう。
現代では花屋などで購入する方法が一般的です。
ただしススキは日持ちしないので、当日もしくは2日以内くらいに
購入することがオススメと言えます。予約をしておくと確実でしょう。
●収穫した野菜や果物
里芋など旬の野菜や果物を一緒にお供えし収穫に感謝する
習わしが所以です。また葡萄などのつるものをお供えすれば
お月様との繋がりが強くなるとの言い伝えも存在します。
お供えをする時は、位置関係が大切です。
日本古来からの考え方では左が上位とされています。
その為、お月様から見て左側にススキなどの自然の物を
右側に月見団子などの人工のものを供えることが基本です。
お月様から見える場所や床の間に飾りましょう。
月見団子は三方に白い紙を載せてその上に飾ることが伝統ですが
三方がない場合はお盆やお皿などに載せれば大丈夫です。
月見団子は子どもが盗んでも良いとされていたことから
昔は微笑ましい団子泥棒が家を回っていたこともあります。
しかし近年ではこの風習は廃れつつあります。
お供えしたものは家族で食べることが基本です。
お月見を楽しんだ後は、おいしいお団子に舌鼓を打つと良いでしょう。
まとめ
世界の慣習と照らし合わせてみると
お月見がより味わい深く感じられますね。
中秋の名月・十五夜のお月見を楽しんでみませんか?
スポンサーリンク