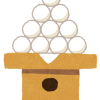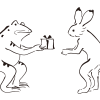言葉の響きも美しい十六夜の月は、商品の名称や歌詞などに
使われることも多く、人々に愛されてきました。
今回は、読み方や時期、意味も含めて十六夜の月に関して
ご紹介します。別名や楽しみ方などもまとめてみました。
十六夜の月の読み方とは?
十六夜の月は「いざよいのつき」と読みます。
「いざよう」という言葉は、「ためらう」という意味合いを含んだ動詞です。
十六夜の月は満月より少し欠けた形をしています。
新月から数えて16日めの月である十六夜の月は
満月に近い15日めの月に比べてやや月の出が遅いことから
まるで月が出るのをためらっているようだと見立てたことが
名称の由来とされています。
月の出は1日50分くらい遅れます。
月の名前が満月から十六夜、次が立ち待ち月、居待ち月
そして寝待ち月となるように、昔の人は、月の出を心待ちにして
名付けていたことがわかるでしょう。
今でも電灯の少ない田舎に行くと、月明かりの明るさにハッとします。
現代のように夜でも煌々とした人口の明るさがなかった時代は
月の光がより鮮やかに楽しめたことでしょう。
十六夜の月の時期や意味とは?
現代日本では、明治6年から採用された新暦という暦が用いられています。
これは地球が太陽のまわりをちょうど1周するくらいの日数を
1年とする太陽暦です。
正確には365日で1周するわけではありませんのでズレが生じますが
うるう年に調整が入ります。
しかしそれ以前は、月の満ち欠けをもとに、プラスして季節を表す
太陽の動きを組み合わせた太陰太陽暦が活用されていました。
これがいわゆる旧暦です。
月の満ち欠けを基準とすることから、陰暦とも呼ばれます。
陰暦では1年は約354日です。
十六夜の月とは、陰暦で16日の夜の月、もしくは陰暦の
8月16日の月を指します。
秋の名物として十五夜がありますが、十五夜も秋にだけあるのではありません。
旧暦の15日の夜は全て十五夜と呼べます。
その為、一般的にお月見をする陰暦の8月15日の月のことを
中秋の名月と特別な名前で呼ぶこともあります。
現在の太陽暦とは異なる暦なので、十六夜の月の日にちは毎年変わります。
旧暦と新暦を照らし合わせ、今年は何日が十六夜の月なのか
確認しておくことがオススメです。
意味に関しては既に出てきたとおり、出てくるのをためらう月という
意味があるとされています。
現代は忙しすぎますが、昔はじっくり月の出を楽しむ余裕が
あったのかもしれません。
月を待ちながら、お酒を楽しむなど、風流な生活が偲ばれます。
十六夜の月の別名や楽しみ方を紹介!
十六夜の月、すなわち陰暦の16日めの月は、既望(きぼう)や
不知夜月(いざよいづき)有明の月とも呼ばれます。
既望とは、望月すなわち満月が過ぎた月という意味合いです。
十六夜の月には夜が明けても沈まない、つまい一晩中夜空に
浮かんでいるという特徴があります。
その為、夜を知らない月=不知夜月、また有明の月とも呼ばれるのです。
豊富な別名からもわかる通り、昔から日本人は月を愛でてきました。
十六夜の月一つを考えてみても、いかに愛されているかがわかります。
気になった方は、月の呼び名を探求してみるのも良いでしょう。
これまでとは違った見方できるようになります。
お月見を楽しんでみるのもオススメです。
基本的には十五夜と変わらずお団子を用意して
ススキを飾って十六夜の月を楽しみます。
必ずしも道具に拘る必要はありません。
奥ゆかしく登場する十六夜の月を待ちながらお酒を嗜むのも素敵です。
また、伝統工芸の中には十六夜の月を題材としているものが
多く存在します。
名前の響きもそうですが、満ち足りた満月よりも
少し欠けたところがある十六夜の月の魅力に魅せられた人は多いです。
東京国立博物館が所蔵している人間国宝・前史雄氏の作品である
沈金漆箱「十六夜」のように、十六夜の月に魅了された人の作品を
探してみるのも面白いでしょう。
現代でも十六夜の月を歌詞に組み込んだ歌などが存在しています。
月を鑑賞しながら歌を聴くのも趣深いですね。
ノンアルコールですが、十六夜という名のカクテルも存在しています。
十六夜の月が由来の名字がある!?
漫画やアニメのキャラクター名として「十六夜」という名字が
使われていることがあります。
現実の世界では、十六夜という名字は、1世帯ほど存在していると
言われていますが、定かではありません。
明治時代の平民苗字許可令によって全ての人が名乗れるようになりました。
地名由来の地名姓などが多いと言われています。
もし十六夜という名字の人が実在しているとしたら
陰暦の十六夜が由来になった可能性がなくもないですが
はっきりと言い切れないでしょう。
まとめ
十六夜の月には独特の魅力があります。
古来から月に特別な思いを託してきた日本人と縁の深い月
なのかもしれません。
今年は十六夜の月でお月見してみるのはいかがでしょうか?
スポンサーリンク