
お彼岸と言えばおはぎを食べる習慣が有名ですね。
適度な甘さと食べごたえがあるおはぎは
子どもから大人まで人気のある食べ物と言えます。
なぜ、お彼岸におはぎを食べるのか、その理由や由来
食べる時期などについて調べてみました。
お彼岸のおはぎの意味を知ることで
より味わい深く楽しめるようになるでしょう。
お彼岸のお供えはどうしておはぎ?理由や由来とは?

お彼岸におはぎをお供えする理由に関してはは様々な説があり
明確に限定はされていません。今回は代表的な説をいくつかご紹介します。
まずは小豆の歴史を振り返ってみましょう。
今ではよく見かける小豆ですが、元々は漢方薬として
中国から輸入されていました。
小豆の野生種は日本でも自生していた記録が残っており
厳密には中国が発祥とも言い難いですが、3世紀頃に伝来した時は
珍しがられていたようです。
小豆独特の赤い色合いは、古代から魔除け・厄除けの意味があるとされ
重宝されます。
特にお米と炊き合わせて炊いた赤飯は、祝の席や儀式に欠かせないもの
として定着しました。
このことから、邪気を払う食べ物としてご先祖様にお供えしたことが
おはぎを食す由来となっているとされています。
また、おはぎは「もち米」と「あんこ」という2つの材料を合わせて
作ることから、ご先祖様の心と現在を生きる私達の心とを合わせるという
意味が込められているという説もあるようです。
さらに、昔は砂糖が非常に貴重な食材でした。
その為、魔除けの小豆と高級素材である砂糖を組み合わせて
作るおはぎを供えることで、ご先祖様に対する感謝の気持ちを
表現したとする説もあります。
現在のようにおはぎを食べる習慣ができたのは江戸時代とされています。
本来、おはぎは供えることがあっても食べるものではありませんでした。
しかし、江戸時代にお彼岸や四十九日の忌明けにおはぎを食べるように
なったとされています。
お彼岸でお供えしたおはぎはいつ食べる?

おはぎをお供えしたら毎日食べないといけないのか?
と誤解されている方も稀にいますが、基本的におはぎは
お彼岸の中日である春分の日と秋分の日にそれぞれ1日だけ
食べれば良いとされています。
これは、捧げたご先祖様がゆっくり味わった後
傷まない内に食べる配慮です。
ただし、厳格に中日でないといけないとされているわけではなく
もし傷みが早そうなら、早めに下げて食べても問題ありません。
大切なのはご先祖様を敬う気持ちです。
形式にこだわりすぎず柔軟に対応しても大丈夫でしょう。
ちなみにおはぎの賞味期限は、3月の春のお彼岸時期で1日程度
9月の秋のお彼岸時期では半日程度と言われています。
もし腐ってしまうと、酸っぱい匂いや味がしますので注意しましょう。
お彼岸でお供えするのはおはぎ?ぼたもち?
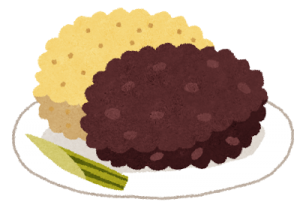
基本的に春のお彼岸にはぼたもちを、秋のお彼岸にはおはぎを
お供えします。
しかし、実際はどちらもほぼ同じものです。
違いがあるのはあんこの種類と言えます。
春のぼたもちはこしあんを、秋のおはぎには粒あんを使用するのです。
この違いは小豆の収穫時期とも関わりがあります。
小豆は5~6月に種まきをして、9~11月に収穫されます。
その為、秋のお彼岸の頃の小豆はとれたてで皮も柔らかく
皮ごと使う粒あんに適しています。
対して春のお彼岸の時期は皮が固くなっているので食感を
考慮し固くなった皮を取り除いて作るこしあんを使ったと
言われています。
しかし現在では春でも皮ごと使える小豆が登場していますので
このような使い分けがあまり意味をなさなくなっていると
言えるでしょう。
現にお店に行くと、春でも秋でもこしあんも粒あんも
両方購入することが可能です。
その為今では、こしあんのものでもおはぎと一緒くたに呼ぶこともあります。
名称に関しては、こしあんを使ったぼたもちは牡丹の花を
粒あんを使ったおはぎは小豆の赤い粒を萩の花に見立てたと
する説もあります。
昔の人の季節の風情を感じ取る心を読み取れることができるでしょう。
現在では、あまりこだわっていないかもしれませんが
由来を知っておくと何気ない名前が趣深く感じられるかもしれません。
お彼岸でお供えするおはぎの作り方

市販品を購入する方法も良いですが
せっかくなのでおはぎを手作りしてみるのも楽しいです。
簡単な作り方をご紹介します。
|
材料 ・あんこ(こしあんか粒あん) 適量 ・もち米 1カップ ・うるち米 1カップ |
もち米とうるち米を混ぜ合わせて炊飯器で炊きます。
通常より水を少なめにするのがポイントです。
炊き上がったらしばし蒸らして、あたたかい内にすりつぶします。
次に俵型になるように丸めましょう。最後にあんこで包めば完成です。
ラップを使うと綺麗にあんこで包めます。
その土地の風習や家庭によって独自の作り方や分量を
採用している場合も多いです。
気になった方は、おじいちゃんやおばあちゃんに
聞いてみることもオススメできます。
一緒に作るのも面白いですよ。
お彼岸でお供えするのはおはぎだけ?
お彼岸ではおはぎだけでなく、お花などをお供えします。
また、故人が生前好きだったものをお供えすることも一般的です。
他家へ訪問する際は、故人が好きだったお酒やお菓子を
持参すると良いでしょう。
ただし、日持ちをするものを選ぶことが推奨されています。
もし食べ物を好まれないご家庭である場合は
お線香などを選ぶと相手も喜んでいただける確率が高まります。
一番大切なのは気持ちです。
亡き人を偲ぶ気持ちが伝わる贈り物を選ぶようにすれば
間違いないでしょう。
不安な時はお店の人に相談し、一緒に選んで貰う方法も有効です。
ちなみにお彼岸のお供え物にはのし紙を付けます。
地域によって違いがあり、関東では黒白の水引ですが
関西では黄白の水引です。
同じ悲しみが繰り返さないようにという意味を込めて
水引は「結切り」を使います。
水引の上部には「御供」もしくは「お供え」と書き
下部にはフルネームを記載します。
薄墨にこだわらなくても大丈夫です。
ただし、丁寧に1文字1文字書くことを心がけましょう。
お彼岸でお供えのおはぎを置く前にすること

ずばり、掃除です。
普段なかなか行えない仏壇や仏具の掃除を行いましょう。
そもそも仏壇は先祖代々をお祀りする祭壇にあたります。
しかし、こまめに掃除をしている人はむしろ少数かもしれません。
お彼岸は春と秋の2回訪れますが
その機会にしっかり掃除をしておくことが肝心です。
お彼岸前に掃除を済ませておくことが理想ですが
難しい時はできるタイミングで行うことを心がけましょう。
仏壇を掃除する時は、まずご先祖様にお断りを入れます。
手を合わせて「これからお掃除をさせていただきます。
少々バタバタするかもしれませんが
心を込めて掃除させていただきますので、ご了承ください」
という旨をお伝えしましょう。
そして写真を撮ります。
なぜなら位置がわからなくなってしまうからです。
初めて掃除をする時にありがちなのですが
写真を撮っておかないと位置関係がわからなくなってしまい
戻せなくなるということがよくあります。
紙に書いておく方法でも構いませんので
しっかり記載しておくようにしましょう。
次に取り出せる仏具を全て取り出します。
出してみると意外と数が多いことに驚く方も多いです。
1つ1つ意味があるものですので、もし知らない仏具があったなら
これを機会に意味や役割を調べておく知識が深まるでしょう。
全て取り出せたら、上からホコリを払っていきます。
水拭きは厳禁です。
ハタキやハケ、細かい所は綿棒などを使って綺麗にしてあげましょう。
全て綺麗に出来たら、仏具を戻して、掃除終了の報告をしてお終いです。
後は綺麗になった場所におはぎなどをお供えします。
心持ちご先祖様も喜んでくれていると感じられるのではないでしょうか。
お彼岸にはお膳をお供えする!おはぎの飾り方は?
お彼岸期間中は、お仏壇にお霊供膳と呼ばれるお膳を備えします。
基本はご飯と一汁三菜の精進料理です。つまり生臭物を使用しません。
専用の御前と器を使うことが正式とされています。
御前の上に5つの器をのせ、仏様が召し上がるように向きに
配慮して配置します。
ただし、負担になるようなら無理をする必要はありません。
自分たちが食べるものと同じものをお供えすれば良いとされています。
基本的にはその日の内に下げ、家族で分け合って食べるものです。
ただし、風習や宗派によって違いがある場合があります。
もし気になる時は、菩提寺に相談してみましょう。
その地方や宗派の正しいやり方を教えてくれます。
おはぎは、特別に飾り立てる必要がないとされています。
故人へ捧げる気持ちをもって、普通にお供えしてあげましょう。
最後には下げて食べます。
傷みが早いようなら、早めに下げて食べても良いです。
春と秋では気候も違いますので、状態をよく見ておくようにしましょう。
お彼岸のお供えのおはぎと並ぶ定番!お花を長持ちさせる方法

お彼岸にはお花も欠かせません。
7日間の期間がありますので、日持ちするお花を選ぶことがポイントです。
仏花として有名な菊やカーネーションの他に、季節を感じられる花や
故人が好きだった花を組み合わせると良いでしょう。
水を毎日取り替えて、水切りすると長持ちしやすいです。
花が弱ってしまう原因は主に水不足にあります。
切り花は切り口から水を吸い上げていますので
切り口が悪いと十分な水が吸えず枯れやすいです。
飾る前に水中で切り口をスパッと切りましょう。
斜めに切れば断面積が広がるので吸い込みがよくなります。
可能ならば毎日水切りすると持ちが良いです。
花を購入した時に延命剤を買い使用するという方法もあります。
まとめ
食べておいしいだけでなく昔から日本に馴染み深いおはぎ。
今年のお彼岸では、意味や由来を噛み締めながら飾り
味わってみてはいかがでしょうか。
スポンサーリンク











