
五節句のひとつとして知られている重陽の節句ですが
実は最近になって重陽の節句が注目を浴びるようになっています。
そういった中で重陽の節句の楽しみ方を思案する方も多くなっています。
重陽の節句にはさまざまな楽しみ方があるのですが
食べ物や和菓子であれば誰でも気軽に楽しむことができます。
しかしながら、重陽の節句ではどのような食べ物や和菓子を
食べればいいのでしょうか。
ここでは、重陽の節句の食べ物や和菓子についてお話し
していきたいと思います。
重陽の節句の食べ物について!
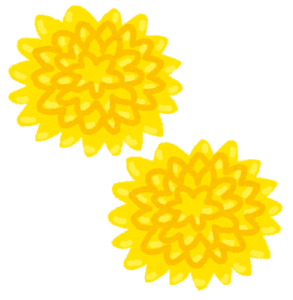
まずは、重陽の節句の食べ物についてです。
日本には重陽の節句を含めてさまざまな行事があり
それぞれの行事に行事食というものがあります。
この行事食を取り入れることによって、よりその行事を
楽しむことができるのです。
重陽の節句は菊の節句とも呼ばれるだけあって
その行事の主役というのはやはり菊になります。
菊を飾ったり菊を眺めたりしながら
菊の花びらを浮かべた菊酒というものを楽しむのが定番です。
ただ、お酒が飲めないという方もいるかと思います。
お子さんのいるご家庭でもお酒は控えておきたいところです。
そういった場合には、食用菊を活用してみましょう。
菊というと仏花のイメージがありますが、食用の菊も多くなっています。
最近では、食用の花を使ったスイーツが注目されていることもあり
食用の花はじわじわとその人気を高めているのです。
もっとも身近な食用菊というと、おそらくお刺身についてくる菊です。
お刺身の場合にはお刺身がメインで、それを引き立てるのが食用菊です。
しかしながら、重陽の節句では菊が主役になります。
食用菊を使ったメインメニューを実践していきましょう。
食用菊を使ったお吸い物やおひたし、天ぷらなどであれば
自宅でも簡単にできます。
もしちょっと凝った料理がいいという場合には
会席で出るような菊花の葛椀といったものに
チャレンジしてみるのもいいかもしれません。
また、重陽の節句では菊だけではなく、栗もいただきます。
というのも、重陽の節句は菊の節句とも呼ばれているのですが
農村では栗の節句とも呼ばれているのです。
実際に、重陽の節句というのはちょうど秋ですし
秋の味覚といえばやはり栗です。
重陽の節句で栗をいただく場合には
主に栗ご飯でいただくことになります。
多くの場合、栗ご飯として食べられます。
栗ご飯であれば簡単にできますし
この栗ご飯に食用菊の花びらを散らしてもいいでしょう。
食用菊と栗以外だとナスも重陽の節句の食べ物です。
ナスは夏野菜炒めといったメニューで使われることも多いですし
夏野菜のイメージが強いという方も多いでしょう。
ただ、秋ナスというものがありますし
秋ナスは嫁に食わすな」という言葉もあります。
「九日(くんち)にナスを食べると中風にならない」という話もあり
重陽の節句には欠かすことのできない食べ物とされています。
ちなみに、中風というのは発熱や発汗、咳、頭痛、肩のこり
悪寒のことを指します。
シンプルに焼きナスにしてもいいですし
煮びたしや天ぷらなどでもいいでしょう。
ナスの紫と栗や菊の黄色というのは相性がいいので
見た目にもかなり鮮やかになります。
食卓がちょっとした芸術作品になるかもしれません。
重陽の節句には和菓子も!
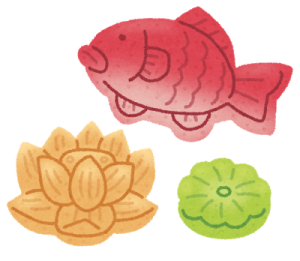
先では重陽の節句の食べ物についてご紹介しましたが
重陽の節句では和菓子も行事食のひとつになります。
菊や栗をモチーフにした和菓子をいただくのも重陽の節句の楽しみ方です。
菊や栗をモチーフにした和菓子にもいろいろなものがあります。
まずは、らくがんです。
穀粉に砂糖、少量の水、水あめなどを加えてよく混ぜて
それを木型に詰めて抜き取り、加熱乾燥して作る打ち物菓子と
いうものの一種になります。
使われている材料によって口どけが違って
そういったところもなかなか面白いです。
ベタベタしないので、手軽に食べられる和菓子のひとつでもあります。
和菓子屋さんはもちろん、スーパーなどでも売っていることがあります。
身近な和菓子です。
次に、ねりきりです。
「和菓子といえばねりきり!」という方も多いのではないでしょうか。
和菓子の代名詞といっても過言ではありません。
ねりきりというのは、煉り物の一種で上生菓子に分類されます。
あんを作るときによく煉るから、ねりきりと呼ばれています。
白あんに砂糖を加えて火にかけてよく煉って
つなぎにみじん粉や求肥などを加えて作られます。
木型に押し付けるだけのシンプルなものもあれば
職人さんがひとつひとつ手作業で細工をしているものもあります。
和菓子でありながらひとつのインテリアになるような
芸術性の高さがあります。
色も豊富で、季節を感じられるものが多いのも特徴です。
見た目にも綺麗な和菓子だからこそ
昔からさまざまなシーンで使われてきました。
続いて、こなしです。
こなしはねりきりに似ているのですが
あんに小麦粉やもち粉などを混ぜて蒸して
さらに砂糖を加えながら手で揉みこなして仕上げたものになります。
揉みこなして仕上げるからこなしと呼ばれているのです。
職人さんによって細かい細工を施されることもありますし
包み生地として使われることもあります。
結構粘りのある和菓子になります。
さらに、きんぎょくです。
中で金魚が泳いでいるような透明な和菓子を
見たことのある方も多いでしょうが、それがきんぎょくになります。
ようかん風でありながらゼリー状の和生菓子という不思議な代物です。
寒天に砂糖や水あめをまぜ、型に流して冷やし固めたものです。
透明や半透明の和菓子で、最近では七夕のシーズンに七夕を
モチーフにしたきんぎょくが売り切れるといったことも多くなっているようです。
あとは、淡雪羹(あわゆきかん)です。
卵白の細かい泡に寒天を入れて固めたもので
口の中でしゅわっと溶けるような和菓子です。
シンプルなものが多いのですが
他の和菓子と組み合わせていろいろなモチーフで
提供されています。
栗をそのままストレートに使っている和菓子も
多い傾向にあります。
栗あんや栗を混ぜた白あんを詰めた
小判形や栗形のまんじゅうであるくりまんじゅうは
定番です。
くりようかんもくりまんじゅうと同じくらい定番なのですが
くりようかんには2種類あります。
ひとつは小豆の練りようかんの中に密漬けした栗を入れたもの
もうひとつは小豆を使用せず本当に栗だけを練って
あんにしたものです。
重陽の節句で楽しむならこういった菊や栗をモチーフにした
和菓子にしましょう。
重陽の節句の和菓子ならやっぱりとらや!

重陽の節句の和菓子なら
やはり老舗であるとらやがおすすめです。
室町時代後期に京都で創業したと言われているとらやは
日本を代表する和菓子の老舗です。
実際に、とらやでも重陽の節句にちなんだ
和菓子は毎年出ています。
菊をモチーフにした和菓子では
過去に菊の露というものが出ています。
重陽の節句には菊の花に綿を被せて
その綿についた露と香りで身を清めるという
被せ綿という風習があるのですが、それを再現した和菓子になります。
紅色の菊形の上に菊の露を表す新引粉がまぶしてあります。
紅色の菊はようかんで、中に白餡が入っています。
菊モチーフの弥栄という最中もあります。
菊の花をかたどった最中は定番ですが
やはり可愛らしいものです。
また、栗をモチーフにした重陽という和菓子も出ています。
重陽の節句限定の和菓子で、桃山の場合には中に
新栗を刻んだ栗餡が入っています。
桃山ではないノーマルな重陽はようかん製で
その中に栗餡を包み、けしの実をまぶしています。
どちらも新栗が入荷しなければ販売されないそうです。
とらやといえばようかんが有名ですが
新栗を使った栗蒸羊羹もあります。
通常のようかんとは違った食感で
栗のおいしさが口いっぱいに広がります。
重陽の節句で和菓子に合う飲み物は?
重陽の節句の和菓子についてご紹介しましたが
和菓子に合う飲み物についてもご紹介しておきたいと思います。
和菓子は意外にお酒にも合います。
菊の花びらを浮かべた菊酒でもいいのですが
ちょっとこだわって漬け込むタイプの菊酒に
チャレンジしてみてもいいかもしれません。
漬け込むタイプの菊酒の作り方は、一般的な果実酒と同じです。
食用菊をよく洗って水気を切り、菊と氷砂糖を交互に容器に入れて
アルコール度数の高いお酒を入れていきます。
そのまま密閉して冷暗所に1カ月以上保管するというだけなのですが
難点はすぐには完成しないというところです。
菊のエキスが染み出ているお酒ですので、花びらを浮かべただけの
菊酒とはまた違った味わいになります。
「菊酒もいいけどお酒はちょっと・・・」という方の場合には
お茶にしてみましょう。
というのも、菊花茶というものがあるのです。
菊花茶には嬉しい効能もありますので、和菓子をいただきつつ
体を労わることができます。
体の中や外の余分な熱を取る、目の充血を改善する
腫れ物などの炎症を鎮める、老化の抑制、香りによる
リラックス効果などが期待できます。
多少癖のあるお茶ではありますが、重陽の節句で和菓子に
合わせるのには最適です。
まとめ
重陽の節句ならではの食べ物を積極的に取り入れていきましょう。
重陽の節句なら和菓子もおすすめです。
老舗のとらやで重陽の節句限定の和菓子をチェックしてみるのも
いいかもしれません。
スポンサーリンク










