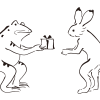七五三では神社にお参りすることになるのですが、
そこで必要になってくるのが初穂料です。
初穂料はのし袋に入れるという方が多いかと思うのですが
のし袋にもいろいろな種類があります。
七五三の初穂料のときにどののし袋を使えばいいのか
わからないと頭を抱えてしまう前に、のし袋の種類を覚えてしまいましょう。
七五三の初穂料を包むのし袋で悩む方は多い!

お子さんの晴れ舞台ということもあって
七五三に気合いを入れる親御さんは多いものです。
神社へお参りするときには初穂料を包むのですが
実はこのときののし袋で悩む方が多いようです。
いつどののし袋を使うのかというのは
なかなか人には聞けないですよね。
恥ずかしく思っている方も多いでしょうが
実際にはのし袋で悩む方は多いので安心してください。
それにのし袋というのは複雑に思えるかもしれませんが
意外に簡単にその種類を覚えられるものです。
七五三をきっかけにのし袋の種類について
さくさくっと覚えてしまうといいでしょう。
のし袋の基本的な種類はたったのこれだけ!
七五三の初穂料をのし袋に包むといっても
のし袋にもいろいろな種類があります。
特に、最近ののし袋というのはオシャレなデザインのものもあって
棚にずらっと並べられていると圧倒されてしまうほどです。
あまりの豊富さにのし袋に圧倒されてしまう方もいるかもしれませんが
基本的なのし袋の種類というものをしっかりとおさえておけば安心です。
のし袋の種類をチェックするときには、水引の形を見るようにしましょう。
基本的な水引の形というのは、たったの3種類です。
これを覚えてしまえば、のし袋で頭を抱えることもなくなるでしょう。
蝶結び

まずは、蝶結びという水引の形についてです。
これは花結びとも呼ばれるのですが
リボンのような形をした水引のことを指します。
蝶結びは婚礼以外のお祝い事で使われるものです。
何度も結び直すことができますので
何度あってもいいようなおめでたいことに適した水引です。
実際に、蝶結びの水引には何度も繰り返したいという願いも込められているのです。
結切り

次に、結切りという水引の形についてです。
これは固結びとも呼ばれる形になります。
切り端が上を向いているものですね。
これは先ほどの蝶結びと違って、結び直すことはできません。
そのため、結切りには、固く結ばれてそれがほどけないように
繰り返さないようにといった願いが込められているのです。
例えば、結婚や退院というのは繰り返したくないものですよね。
そのため、この結切りという水引は婚礼や快気祝いといった
繰り返すことが望ましくないお祝い事に適しているのです。
鮑(あわび)結び

そして、鮑結びという水引の形についてです。
これは鮑切り、あわじ結びといった呼び方をすることもあります。
だいたい水引と聞いて思い浮かべるのがこの鮑結びの水引です。
鮑結びは、ほどくことができないわけではないのですが
ほどくのが難しい結び方です。
そのため、いつまでも続くという願いや意味合いが込められています。
形が鮑に似ているため、鮑結びと呼ばれるのですが
鮑というのは長寿の象徴でもあります。
そのため、慶事でも弔辞でも使われる水引になります。
細かく見ていくと他にも水引の形はあるのですが
基本的にはこの3種類です。
形の他にも色の違いがありますが、色は簡単です。
白と赤、金と赤の組み合わせは慶事用
白と黒の組み合わせは弔辞用
白と金の組み合わせはその両方で使うことができます。
色に関してはわざわざ覚えなくとも
何となく知っていたという方も多いのではないでしょうか。
では七五三の初穂料のときに相応しいのし袋とは・・・?
先ではのし袋の種類についてお話ししましたが
では七五三の初穂料のときにはどののし袋がいいのでしょうか。
結論から言ってしまうと
七五三の初穂料を包むときには蝶結びの水引ののし袋が適しています。
七五三というのは何度あっても嬉しいお祝い事です。
おめでたいことなので、白と赤の組み合わせの水引にしましょう。
のし袋の種類を覚えておくと
お祝い事の性質からのし袋の種類をしぼり込むことができますので
七五三以外でも役立ってくれるはずです。
まとめ
七五三の初穂料を包むときののし袋で悩む親御さんは多いものです。
しかしながら、のし袋の種類を覚えてしまえば
これから先の行事で悩むこともなくなるでしょう。
簡単なのでこの機会に覚えてしまいましょう。
スポンサーリンク