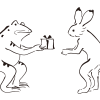7歳の七五三というのは、まさに最後の七五三です。
親御さんとしては、最後ということもありかなり気合いが入るのではないでしょうか。
七五三の7歳のお祝いというのは、「帯落としの祝」「帯解きの祝」とも言われています。
女の子は7歳で初めて付け紐をはずし、大人と同じように帯を締めるという儀式は伝わっており
それが7歳の七五三でのお祝いにつながっているのです。
親御さんとしてはまだまだ子どもという感じでしょうが
七五三で身につける着物では一足早く大人の仲間入りをするわけです。
ここでは、7歳の七五三での着物の違いや女の子のための選び方について
お話ししていきたいと思います。
七五三の着物は7 歳と3歳で何が違うの?

女の子は7歳と3歳で七五三のお祝いをするのですが
そのときの着物に違いがあるということをご存知でしょうか。
というのも、七五三の女の子の着物は
3歳のときに着る着物と7歳のときに着る着物では着物そのものの作りが違ってくるのです。
3歳のときの七五三では、三つ身というお腹周りの締めつけがゆるい幼児用の着物を着ることになります。
一方で、7歳のときの七五三では大人と同じように帯をつける四つ身という子ども用の着物を着ることになります。
子ども用とは言え、作りは大人の着物と同じです。
ただ、今の時代、着物というのは子ども用のものでもやはりある程度の金額になります。
お子さんの将来のために少しでもお金を残しておきたいと節約志向で来ている方であれば
3歳と7歳で同じ着物を使い回したいと思うこともあるかもしれません。
確かに気持ちはわかるのですが
やはり3歳と7歳の七五三ではそれぞれ別の着物を用意してあげたほうがいいでしょう。
実際に、3歳のときと7歳のときでは七五三に必要な小物も変わってきます。
3歳のときには3歳用のものを、7歳のときには7歳用のものを着せてあげるようにしたいものです。
「それでも同じもので!」という強い意志があるなら
3歳のときの七五三の時点で大きめの着物を用意しておくしかありません。
ただ、3歳のお子さんにとって大きめの着物というのは思っている以上に負担になります。
それでなくとも3歳のお子さんにとっては、着物そのものが窮屈に感じられるのです。
大きめの着物を用意するとなると、生地の重さが増えますし、かさばります。
最近では、3歳と7歳とで兼用できる仕様の着物もあるようですので
できるだけお子さんの負担を減らせるように着物を選んでいきたいものです。
ですが、基本的に七五三の儀式の意味というものを考えれば
3歳と7歳では別々の着物を用意するのが筋です。
お子さんの負担も考えれば、3歳と7歳で別々に着物を用意するのが最善といえるでしょう。
七五三の着物!7 歳で必要になる小物は?

7歳の七五三のために着物を用意すれば、それでOKというわけではありません。
先でもお話ししましたが、3歳の七五三と7歳の七五三では用意する小物が違ってきます。
ここでは、7歳のときの七五三で必要になってくる小物についてお話ししていきましょう。
まずは、襦袢です。
ご存知かとは思いますが、襦袢と書いて「じゅばん」と読みます。
着物の下に着て、着物に汚れがつかないようにするためにものです。
感覚としては普段着ているタンクトップやキャミソールと同じようなもので
着物のための下着といったところです。
上下でわかれている2部式になっている襦袢もありますし
上半身だけの半襦袢というものもあります。
子ども用のものであれば、腰紐で縛らなくてもOKなマジックテープ式のものも多いでしょう。
マジックテープ式のものは着付けをかなり楽にしてくれるのでおすすめです。
この襦袢の衿の部分に半衿というものを縫い付けます。
しかしながら、すでに襦袢に半衿が付いた状態のものも売られています。
こういったものであれば、縫い付ける手間を省くことができますので
親御さんにとってはありがたいものです。
レンタルのものやセットで売られているものには
襦袢はついていないことがほとんどです。
注意しておきましょう。
先でも少し登場した半衿なのですが、半衿と書いて「はんえり」と読みます。
襦袢に縫い付ける衿なのですが、この半衿の部分は着物の外からも見えるようになっています。
親御さんで半衿を縫い付けるか、最初から縫い付けてあるものを選ぶかになってきます。
着物をレンタルする場合には、半衿はついていないものを思っておいたほうがいいでしょう。
また、着物からチラっと見えるのが重ね衿です。
重ね衿は着物を重ねて着ているように見せるためのものです。
これは機能性というよりも、どちらかというと着物をよりオシャレに見せるための小物になります。
基本的には着物に縫い付けてあるので、親御さんがどうこうする必要はありません。
ただ、もし着物をゼロから仕立てるとなった場合には
この重ね衿についてもしっかりと考えておく必要があります。
7歳の七五三では帯も必要になってくるのですが
大人のように一枚の長い帯を用意することはほとんどありません。
というのも、すでに結んだ形になっている結び帯を使うことがほとんどなのです。
結ぶ手間が省けるというだけではなく、帯の量が少なく済むので軽くなります。
着崩れしにくいのもありがたいところです。
着物との相性はもちろんですが
後ろから見たときの印象も考慮して選んでいくといいでしょう。
帯揚げと志古貴も必要になってきます。
ちなみに、志古貴は「しごき」と読みます。
帯揚げというのは、帯の上からのぞく部分です。
志古貴とは帯の下からのぞく部分のことを指します。
もともとは帯揚げも志古貴も帯の形が崩れるのを防ぐためのものです。
しかしながら、先でもお話ししましたように7歳の七五三の帯というのはほとんどの場合で結び帯になります。
つまり、基本的に型崩れすることがないのです。
そのため、帯の形が崩れるのを防ぐというよりは
装飾のための小物と考えていいでしょう。
帯がほどけないように、帯の結びの中を通して結ぶ帯締めも必要になります。
セットになっているものやレンタルのものであれば
着物や帯に合わせたものがついてくるかと思います。
セットやレンタル以外で帯締めを用意する場合には
着物や帯に合わせて選ぶ必要があります。
あとは、筥迫と末広も必要な小物です。
筥迫は「はこせこ」と読みます。
末広は扇子のことです。
筥迫は、もともとは武家の娘さんが使った紙入れだったのですが
現在では完全な装飾用の小物となっています。
帯色に合わせるのが一般的です。
末広は大人用のものよりも小さいものになります。
大人が末広を差す場合には帯と着物の間ですが
七五三でお子さんが差す場合には帯と帯締めの間になります。
そして、足元に関する小物も必要になります。
足袋に関しては履きにくさが不安要素になるという親御さんも多いかと思うのですが
最近の足袋はストレッチ素材でできています。
そのため、お子さんにとってもかなり履きやすいかと思います。
足袋というと白の無地というイメージがありますが、最近では色ものもありますし
さらに刺繍やラインストーンが入ったものまであります。
着物とのコーディネートを楽しんでみてもいいのではないでしょうか。
足袋もセットやレンタルの場合には入っていないことがほとんどです。
その点は注意しておきましょう。
足袋を履いたら今度は草履です。
草履もいろいろなものがあるのですが
基本的には鼻緒の色を着物の裾の色と合わせるといいと言われています。
草履の代わりに木履、いわゆるぽっくりを履かせるというのもひとつです。
ちなみに、草履であればバッグとお揃いのセットも多いので
バッグのコーディネートも一緒に楽しめるでしょう。
七五三の着物における女の子のための選び方

最後に、七五三の着物における女の子のための選び方についてお話ししておきましょう。
女の子ということもあり、親御さんもかなり気合いが入るかと思います。
しかしながら、親御さん以上におじいちゃんおばあちゃんが
張り切っているというケースも多いのではないでしょうか。
実際に、お金を出してもらう分
おじいちゃんおばあちゃんの意見も反映させるというケースも少なくありません。
親御さんにしてみるとおじいちゃんおばあちゃんの意見が
大きく反映されるとちょっと面白くない部分もあるかもしれません。
ですが、七五三の着物に関しては結果的におじいちゃんおばあちゃんに
任せてよかったという親御さんも多いのです。
着物を選ぶときには、おじいちゃんおばあちゃんに選んでもらうのもいいかもしれません。
また、7歳にもなると、お子さん自身もしっかりと考えて選ぶことができます。
一番いいのは、やはりお子さんの希望を反映させた上で着物を選んでいくことでしょう。
最近では、レースやフリルをあしらった今時の着物も多くなっていますので
お子さんも積極的に選んでくれるのではないでしょうか。
ちなみに、3歳の七五三では圧倒的に赤系の着物が多くなります。
そのため、赤系以外のちょっと大人っぽい色を選ぶという方も多いようです。
まとめ
七五三の着物はやはり7 歳と3歳では違うものです。
必要な小物も違ってきます。
また、七五三の女の子の着物の選び方もいろいろです。
後悔のない七五三にできるよう慎重に選びましょう。
スポンサーリンク