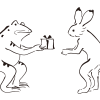お子さんが七五三を迎えるということで
張り切っている親御さんも多いのではないでしょうか。
七五三というと写真撮影のイメージが強いですが
神社へのお参りを忘れてはいけません。
神社へお参りするときには、初穂料が必要になります。
この初穂料というのが親御さんの悩みの種となるのですが
ここではその悩みを解消できるよう初穂料の金額からのし袋の書き方
までご紹介していきたいと思います。
初穂料に関する悩みを解消することができれば
より晴れやかな気持ちで七五三を迎えることができるでしょう。
七五三での初穂料の金額は?

まず、七五三での初穂料の金額です。
お金を包む以上、やはり他の人がどれくらい包んでいるのか
という部分が気になってしまうものです。
基本的に神社で「最低でも○○円出してください」と
言われることはほとんどないでしょう。
というのも、神社というのは「お気持ちで」というスタンスなのです。
ただ、いくら「お気持ちで」と言われてもあまりにも
少ない金額を包んでしまうと失礼になってしまうのではないかと不安になるものです。
そういった場合には、七五三の初穂料で包む金額の相場
というものを知っておくと安心です。
七五三の初穂料で包む金額の相場というのは
だいたい5000円から10000円だと言われています。
このあたりは神社によっても違ってきます。
七五三の初穂料をいくらからと決めているところもありますし
完全にお気持ちでと参拝者の方に任せているところもあります。
神社のほうで金額を明記していない場合には
相場の範囲内で包むといいかもしれません。
また、お祓いの内容から包む金額を変えるのもひとつです。
だいたいお祓いの内容に関しては、お祓いのみなのか
お祓いの後でお守りやお札をいただけるのかのふたつのパターンになります。
やはりお祓いの後でお守りやお札をいただけるということであれば
お祓いのみのときよりは多めに包んだほうがいいでしょう。
普通に考えて、お守りやお札というのはある程度の金額がするものです。
それに、そのときだけの限定のお守りやお札ということもあります。
もちろん、お参りに行く神社に直接問い合わせをするのもいいでしょう。
「いくら包めばいいでしょうか?」と聞いてしまうと神社のほうも
答えにくいですから、「皆さんはどれくらいを包まれるのでしょうか?」
といった形で聞くようにしましょう。
金額も気になるところではありますが、包む金額によって
お子さんの将来が違ってくるというわけではありません。
仮に十分な金額が用意できなくとも、その分しっかりと
感謝の気持ちを込めるようにすれば問題はありません。
お金に関しては、ピン札を用意すべきかどうかで
悩む親御さんも多いでしょうが、実はどちらでもOKです。
折れているお札だからといって失礼になるわけではありませんが
気になるようであれば事前にピン札を用意しておくといいでしょう。
ただ、折れているお札でも失礼にはならないといっても汚れていたり
ボロボロになっていたりするのであれば、別のお札を用意したほうがいいでしょう。
気持ちが大事とは言っても、七五三というおめでたい行事で
神様の前に立つということを考えれば、あまり適当なことはできないはずです。
初穂料を包むのし袋の書き方は?

七五三での初穂料の金額がわかったところで
今度そのお金を包むのし袋の書き方についてお話ししていいましょう。
初穂料もさながら、こののし袋というのも親御さんを悩ませるものです。
ただ、贈答品売り場の方でない限り、このあたりについて
完璧にマスターしているという方はそういないでしょうから
わからないからといってしょんぼりする必要はありません。
基本的に七五三の初穂料は、のし袋に包む方が多いようです。
こののし袋にもいろいろな種類があるのですが
基本的には紅白で蝶結びの水引ののし袋を選ぶようにしましょう。
中袋のついているものがベストです。
こののし袋の書き方なのですが
できれば筆を使うようにしましょう。
ボールペンが悪いというわけではないのですが
やはり筆で書くのがマナーと考える方は多いものです。
実際に書いてみるとよくおわかりになるでしょうが
ボールペンで書いたときよりも筆で書いたときのほうが
のし袋の見栄えもいいです。
ちなみに、ボールペンよりは万年筆のほうがいいとも言われていますが
万年筆で書いたときの見栄えというのはやはりボールペンで
書いたときと近い感じになります。
ベストなのはやはり筆でしょう。
筆で書くときには、墨の濃さも気を付けておきましょう。
基本的に慶事では濃い墨で、弔事では薄い墨
で書くのが好ましいとされています。
慶事は喜びを表すために濃い墨で書くのがいいと言われています。
「筆ペンは?」という方もいるでしょうが
もちろん、筆ペンでもOKです。
のし袋の表書きでは、水引の上に「御初穂料」「お初穂料」「初穂料」と書きます。
言うまでもないのですが、縦書きで水引にかからないように書きましょう。
そして、次に水引の下に名前をやや小さめに書きます。
当然、これも縦書きです。
うっかり親御さん自身の名前を書いてしまいそうになるでしょうが
ここには七五三でお祓いを受けるお子さんの名前をフルネームで書きます。
中袋の書き方にも注意!

中袋にお金を入れるときには、お札の表がきちんと表向きで
人物が上側に来るように入れます。
ただ、それで終わりというわけではありません。
中袋にも書き方というものがあるのです。
中袋の表側の真ん中に金額を書くというのはなんとなく知っているという方も多いでしょう。
しかしながら、普段の領収書のように「¥5000」なんて書き方をしてはいけません。
中袋に初穂料の金額を購入するときには
表側の真ん中に「金○○円也」と縦に書きます。
このとき、漢数字を使うのですが、普段使う漢数字というと
「一、二、三」を思い浮かべる方がほとんどでしょう。
しかしながら、中袋に金額を記載するときには同じ漢数字でも
「壱、弐、参」といった普段は使わないほうの漢数字をおすすめします。
一は壱に、二は弐に、三は参に、五は伍に、十は拾に
千は仟に、万に萬にすると見栄えもよくなります。
ちなみに、四、六、七、八、九はそのままで問題ありません。
絶対に普段使わないほうの漢数字を使わなければいけない
というわけでないのですが、こちらの書き方のほうがしっくり来ます。
これも実際に書き比べてみると、よくおわかりになるかと思います。
金額を書いて終わりではなく、中袋の裏にもさらに記載すべきことがあります。
中袋の裏側には、住所や氏名を左下の方に縦書きで小さめに書きます。
こちらに記載する氏名は世帯主のものになります。
住所を記載するときには番地などでも漢数字を使うことになりますが
ここで使う漢数字は普段使っている簡単なほうで問題ありません。
中袋の基本的な書き方というのはこのような感じなのですが
場合によってはすでに金額や住所、氏名を記入する欄が用意されていることもあります。
そういった場合には、それに従って記載していけば問題はありません。
中袋の書き方というのは実は地域によって違うところもあるようで
金額も住所も氏名も表に書くというところもあれば
金額も住所も氏名も裏に書くというところもあるようです。
地域で決まりがあるなら、それに従って記載したほうがいいでしょう。
中袋の封はしておいてもしておかなくともどちらでも大丈夫です。
糊付けや〆の記入は必須ではありません。
中袋に関しては、これで問題はないはずです。
のし袋の裏も忘れないように

のし袋の中には、中袋のないものもあります。
もし、中袋のないのし袋を使う場合には
中袋に記載する情報をのし袋の裏に記載しなければいけません。
のし袋の裏には、住所、氏名、金額を記載することになります。
ただ、中袋がないのし袋だからといって
そのままお金を入れるというのはあまり好ましいことではありません。
初穂料というのはお供えや神様への感謝の気持ちを伝えるためのものですから
少しでも丁寧な状態で包んでおきたいものです。
中袋がない場合でも、お金を半紙に包む、別の白封筒にお金を入れる
といった形にしておきたいところです。
また、中袋のあるのし袋の場合でも、裏で下の紙が手前側に来るように
折ることを忘れないようにしておきましょう。
裏の折り方は慶びを受ける上向き、悲しみを流す下向きと表現されますので
一番手前に来るものが上向きになるように折るのが適しています。
のし袋を使わない場合には?

基本的に七五三の初穂料というのは、のし袋に包むものです。
しかしながら、中身に対してのし袋が豪華すぎると気になるという方も多いでしょう。
おじいちゃんおばあちゃん世代だと注意されることもあるかもしれません。
のし袋を使うのが憚られるという場合には、白封筒を使うのもひとつです。
白封筒に関しても、書き方は先でお話ししたのし袋と同じです。
和紙などでお金を包み、それを白封筒の中に入れ
筆で初穂料と書き、金額、住所、氏名といったものを記載していきましょう。
まとめ
七五三での初穂料の金額やのし袋の書き方
中袋の書き方、裏の書き方については
よくわからないという親御さんも多いものです。
一度覚えてしまえばどうってことないので
この機会に覚えてしまいましょう。
スポンサーリンク