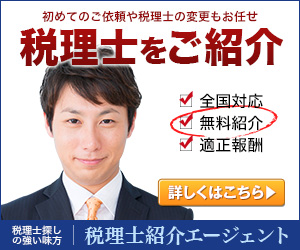会社が窓口となって従業員の所得税を計算し清算してくれる年末調整。
会社が税理士などに任せていることもありますが
自分でできるとより把握しやすいですよね。
今回ははじめてでも理解できる全体の流れや書き方のポイントに関してまとめてみました。
源泉徴収と年末調整とは?

年末調整と言えば所得税の清算であると理解している人が
多いかもしれませんが、本来であれば各個人が確定申告して
納税する流れが自然と言えます。
しかし、日本国民全員が1人1人確定申告すると
税務署としても対応しきれません。
そこで、会社が窓口となり、従業員分の所得税を計算して
給与から天引きという形で納めるというシステムが採用されています。
これが源泉徴収です。
従業員の方なら、毎月の給与明細でいくら天引きされているか
把握しているという方も多いでしょう。
国としても所得税をとりっぱぐれることがなく
従業員にとっては会社が代わりに納税処理をしてくれるので
手間がなく便利であることから、現在も適応されています。
しかし1つ困ったことが生じているのです。
それが、「ズレ」です。
所得税とは「その年1月1日から12月31日までの所得」額に対して
課せられる税金です。
その為、まだその年の所得が確定しない段階で毎月給与から
天引きしていると、正しい金額とズレが生じる事があります。
このズレを所得が確定する年末に調整するのが、年末調整です。
年末調整の全体の流れ
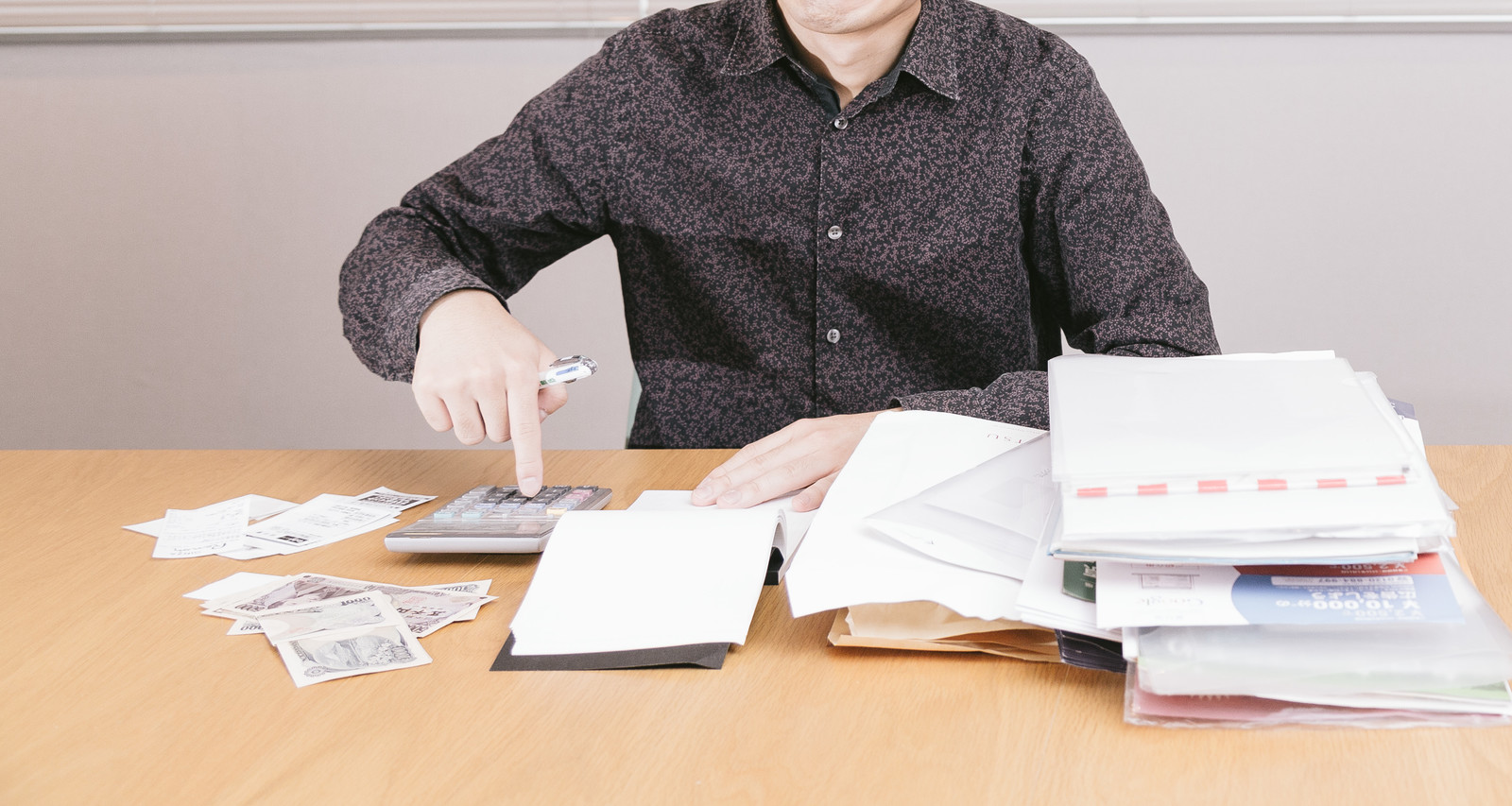
概要がわかったところで、年末調整を行ってみましょう。
ざっくり流れを言うと
所得額を計算しそこから所得控除額を引いて、清算します。
控除が計算されるので、多くの人は還付金を受け取ることになります。
年末調整をする為には、所得額を把握することが必要です。
同時に所得控除の額を割り出す必要があります。
年末調整の必須書類である
「扶養控除等申告書」と「保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書」
を書きながら進めていきましょう。
「扶養控除等申告書」は配偶者控除や扶養控除において必要となってくる書類です。
「保険料控除申告書・配偶者特別控除申告書」は
社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者特別控除などに必要な書類となっています。
こちらの場合、生命保険会社から届く生命保険料控除証明書などの書類の添付が必須です。
書類はまとめて用意しておきましょう。
後は、「年末調整で計算された税額」から「源泉徴収により天引きした税額」を引いて
差額で還付か徴収を行えばOKです。
納税額の過不足分を精算する時は「所得税徴収高計算書(納付書)」を活用します。
年末調整の書き方のチェックポイント

年末調整でややこしくなるのは
自分がどの控除に該当しているか把握できていな為に書類のどこを
記入すればいいのかわからない場合でしょう。
そこで、ポイントを下記にまとめてみました。
以下をチェックしていくと、自分がどの控除に該当しているのか
書類のどこを記入すればいいのかがわかりやすいです。
①配偶者の有無
配偶者がいるなら「配偶者控除」「配偶者特別控除」
以前結婚していたなら「寡婦控除」「寡夫控除」が該当します。
②子供の有無
子供がいる場合、年齢によって該当の控除が変わります。
16歳未満なら「住民税の扶養控除」
19~22歳なら「特定扶養控除」
16歳以上で19~22歳以外なら「扶養控除」をチェックしましょう。
③70歳以上の方がいる場合
配偶者なら「老人控除対象配偶者」
配偶者ではないが扶養にいれていない、
同居している場合は「同居老親以外の者」
同居しているなら「同居老親等」を書きます。
④障がい者を扶養に入れている場合
「障害の程度が1級又は2級その他重度の障害」でなければ「一般の障がい者」
「障害の程度が1級又は2級その他重度の障害」であり、同居していないなら「特別障がい者」
同居しているなら「特別同居障がい者」の欄をみましょう。
⑤控除証明書の有無
該当している場合、控除証明書が届くものもあります。
証明書の内容によって、把握しましょう。
証明書が届くのは
「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「社会保険料控除」です。
ここまでチェックできれば、漏れなく記載できるでしょう。
念の為、記載した後は税理士などのプロのチェックしてもらうと確実です。
何度か繰り返せば、自分ひとりでも問題なく書けるようになります。
まとめ
年末調整は、法律上は源泉徴収票を従業員に配ることになる翌年1月31日までが期限とされています。
しかし、ギリギリは危険です。早め早めに処理することが必要でしょう。
また、もし申告漏れなどの間違いがあった場合でも
翌年1月31日までなら「再年末調整」として修正できます。
過去5年分なら遡って申告することも可能です。
申告し忘れなどがないように、日頃から書類の管理をしっかししておきましょう。
もちろん、最終的に届いた源泉徴収票は、保管しておくことが大切です。
スポンサーリンク