
年末調整の年間所得を書く欄に
ミスをする人が多いということをご存知でしょうか?
年間所得と聞かれて、年収を答えてしまうと実は間違いです。
正確に書類を作成する為にも、年間所得に関して
正しい知識を覚えておくと便利ですよ。
年末調整は年間所得を書く欄がある?

年末調整の年間所得と言えば
「給与所得者の扶養控除等申告書」の「所得の見積額」を記入する際に
必要になってきます。
年末調整の段階では、まだ源泉徴収票はでていませんから
確定額ではなく見積額を書くことになります。
実はこの欄、多くの人が記入をミスしてしまうところでもあります。
「所得の見積額だから、年収を書けばいいのでは?」と考えた方は
残念ながら収入と所得を取り違えていると言えるでしょう。
年収は、言わば1年間の収入の総合計額です。
対して所得とは収入から必要経費を引いた額となります。
「所得の見積額」とある通り
ここで書かないといけないのは「年間の所得額」です。
詳しく見ていきましょう。
「所得の見積額」の記載が必要は場合とは?
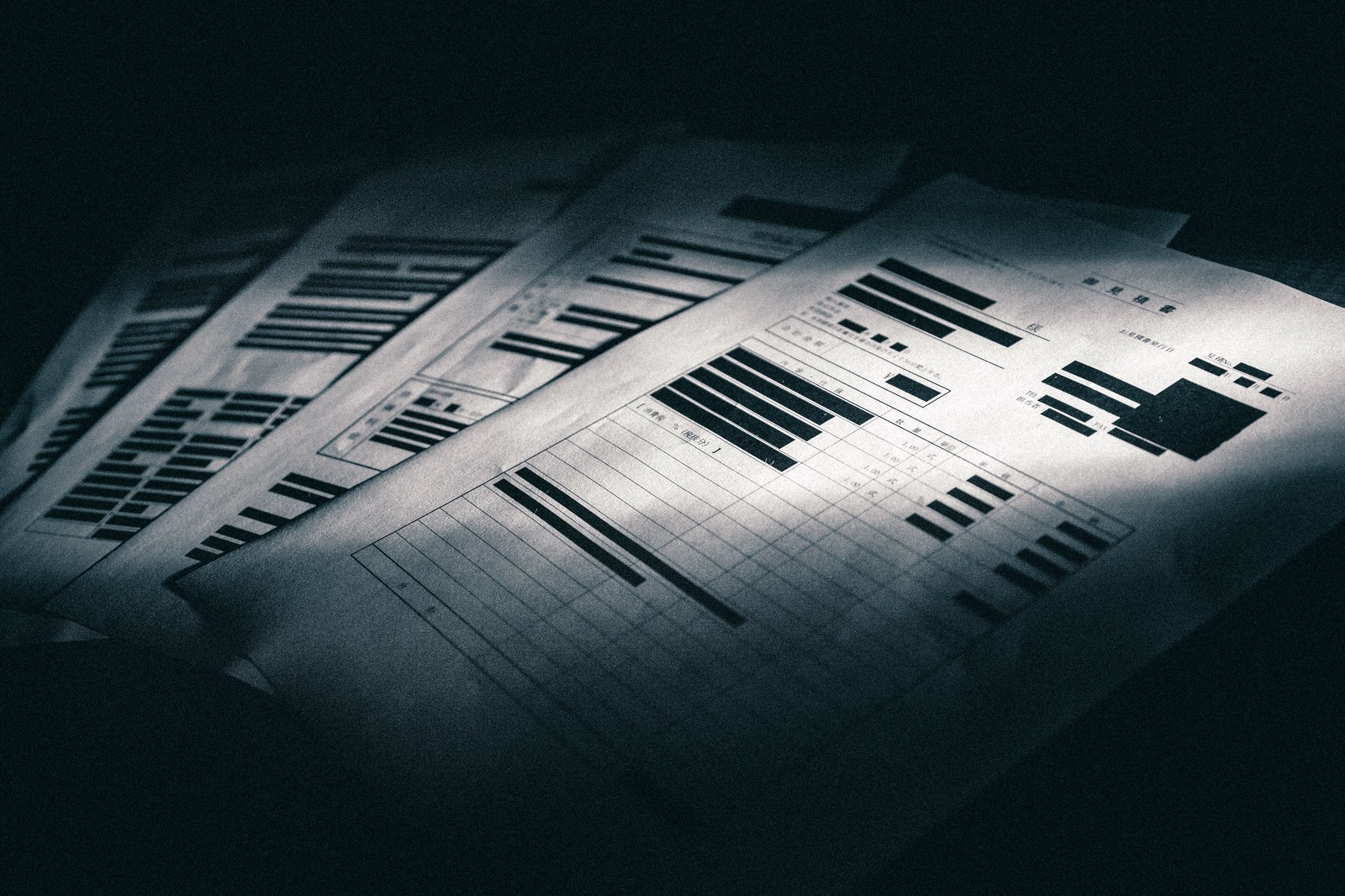
記入が必要なわけではありません。
この欄を活用するのは、「配偶者控除」または
「配偶者特別控除」を適用する場合となります。
年末調整は、会社側からのアナウンスで行う人がほとんどでしょう。
当然納税者の所得額は、会社側が把握していますので
「所得の見積額」で記入するのは控除対象配偶者の年間所得見積額となります。
控除対象配偶者の収入が給与所得であった場合は
収入から給与所得控除である65万円を引いた額を記入します。
給与収入-給与所得控除(65万円)=38万円以下であれば
配偶者控除の対象となるのです。
よく103万円の壁という言葉を聞きますが
給与収入においては103万円が、配偶者控除の対象になる限度額である為
このような表現が生まれてました。
給与所得でない場合は注意!

配偶者の収入が給与所得でなかった場合、注意が必要です。
最近、ネットでビジネスして収入を得る方も増えてきました。
ただし、ネットビジネスでの収入は給与所得ではなく
雑所得や事業所得となります。
つまり、給与所得控除である65万円を引くことはありません。
引けるのはその収入を得る為にかかった必要経費だけです。
たまにネットビジネスをしている方で間で
「103万円稼がなければ大丈夫」と誤解している人がいますが
103万円というのは給与所得の場合の限度額ですので注意しましょう。
ネットビジネスは経費がかからないものも多く
意外とすぐに38万円のラインを突破してしまったりします。
扶養範囲を気にするなら、ネットビジネスを行う時は
配偶者の方と相談しておくことをオススメします。
また、公的年金受給者の場合も、計算式が変わってきます。
65歳未満なら70万円、65歳以上は120万円を
差し引いた後の金額が38万円以下になるかどうかがラインです。
年間所得の見積額が確定額と違ったらどうする?

年末調整を行う時点では、まだ1年間の所得額は確定していません。
その為、見積額との間にズレが生じる場合もあるでしょう。
見積額ですので、必ずしも端数まで合わせたピッタリの額を書く必要はありません。
ただし、年間所得が38万円を越えてしまい扶養控除の対象から外れたなら
不足分の税金を納めなくてはいけなくなります。
その場合は、翌年の3月15日までに納税者が確定申告をして
キチンと税金を納めましょう。
税務署は多く払いすぎていても教えてくれませんが
税金額が少ないと納税者の職場などに電話がかかってきたりします。
特にマイナンバー制度が始まってから
マイナンバーからバレてしまうことが多くなっていますので
間違えないようにキチンと管理しておくことが大切です。
給与所得者なら、忘れずに源泉徴収票を確認しましょう。
自分の認識とズレがなければ問題ありません。
ネットビジネスなどで収入がある人は
自分でしっかり年間所得額を把握してくことが必要でしょう。
2018年以降から変化あり!

2018年以降、配偶者控除に関しては改定・見直しが実施されることが決定しています。
具体的に言うと、配偶者控除は年収103万円→年収150万円
配偶者特別控除は141万円→201万円に基準額が引き上げられるのです。
2018年から変わることを認識しておき
自分は該当しているかどうかチェックしておくことが大切でしょう。
もし不安がある時は、変わり目の時期に
会社の経理担当者や、税理士など詳しい人に相談して確認しておくと確実です。
まとめ
ここまで読んだ方なら、年間所得と年収の違いはバッチリでしょう。
所得と収入はごっちゃに考えてしまっている方も多いですから
今のうちから正しい考え方を把握しておくことが大切です。
社会人としては必須のスキルとなります。
正しく数字を把握できるようになると便利です。
年末調整の際も、書類を迷わず記入できるようになります。
回数をこなしていけば、考え方も無理なくしっくり納得できることでしょう。
スポンサーリンク











