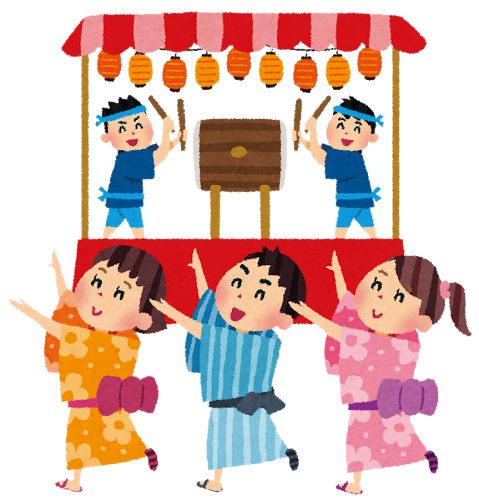
真夏の風物詩である盆踊り。日本人にはなじみ深い行事です。
独特のリズムに合わせてみんなで一緒に踊った経験がある方も多いでしょう。
地域によっては現在でも毎年行われているところもあります。
しかしなぜ盆踊りをするのかとなる理由を知っている方の方が少ないのではないでしょうか?
今回は起源や由来と合わせて盆踊りについてまとめてみました。
盆踊りに込められた意味とは?
盆踊りとは、もともとお盆に帰ってきたご先祖様などの霊を迎え送るための念仏踊りとして始まったとされています。
盆踊りに込められた意味に関しては、複数の説があります。
誰でも分け隔てなく参加することができ、一緒に踊ることでご先祖様や無縁仏など全ての霊を供養できるとする説、成仏できた亡者が喜ぶ姿を表現した踊りであるという説、など成仏に通じる喜びの意味が込められているという捉え方もあります。
その一方で、悪霊やさまよっている亡者たちを踊りながら追い出すという意味があるという説もあります。
皆が楽しく踊る中に誘い込むことで、お盆にやってきた全ての霊を送り出すという意味を含んでいる考え方もあるのです。
現代では娯楽的な意味合いが強くなっていますが、あの世とこの世を繋ぐお盆らしい意味合いが込められていることがわかります。
盆踊りの始まりはいつ?起源や由来について
盆踊りの始まりは、なんと平安時代まで遡ります。
平安時代中期に活躍していた空也という僧侶が、念仏を庶民に広める為、瓢箪(ヒョウタン)を手に持ち叩いて節をつけながら念仏を唱える方法を考案しました。
とっつきにくい念仏もこの方法なら手軽に唱えられると考えたのです。
さらにいつの間にか唱えるだけでなく念仏に合わせて踊りを踊るようになりました。
当時は「空也念仏」とも呼ばれていたそうですが、この手法は「念仏踊り」として世間に広まります。
やがて、先祖を迎い入れ供養する盂蘭盆会、いわゆるお盆と結びつき「盆踊り」が誕生しました。
時代が下り鎌倉時代になると、時宗の開祖である一遍上人(いっぺんしょうにん)が全国に盆踊りを広めます。
一遍上人は全国を行脚し、その独自スタイルで非常に人気が高かったこともあり、盆踊りが全国的な行事として定着する礎を築き上げました。
江戸時代は少々娯楽色が強くなり、本来の宗教行事から離れて、各地域との交流や男女の出会いの場として利用されるようになります。
男女の出会いの場になったことで、問題も発生するようになり、明治時代には警察の取締が行われました。
その為一時盆踊りは衰退しますが、大正時代の末期頃から再興し、現在では再び日本各地で行われるようになっています。
もともと盆踊りの晩は旧暦7月15日なので満月です。
照明のない時代でも人々は明るい月明かりのもと、楽しく踊ることができたのでしょう。
盆踊りの起源は以外に古く、その長い歴史の間に様々な色合いを見せていたことがわかります。
有名な日本三大盆踊りとは?誰もが聞いたことがある定番の曲も紹介!
現代の盆踊りは、地域交流の側面が大きいように思われます。
特に有名なのは、秋田県の「西馬音内盆踊り」、岐阜県の「郡上八幡盆踊り」、そして徳島県の「阿波踊り」でしょう。
総称して日本三大盆踊りと言われています。
「郡上八幡盆踊り」は別名亡者踊りとも呼ばれています。
お囃子は野性的ですが、踊りは上方風の優美な仕様に仕上がっています。
印象的なのは独特の編み笠や目の穴だけあけた黒い彦三頭巾を頭からすっぽりかぶり、顔を隠してしまうことでしょう。
初めて見た人はその不思議な光景に思わず引き込まれてしまいます。
現在では国指定重要無形民俗文化財にも指定されています。
「郡上八幡盆踊り」は、地元の人も観光客も分け隔てなく一つの輪になってみんなで踊ることが特徴的です。
これは江戸時代頃に「盆の4日間は身分の隔てなく無礼講で踊るがよい」と奨励されたことが影響していると言われています。
こちらも国指定重要無形民俗文化財となっています。
「阿波踊り」は、全国的に極めて知名度の高い踊りと言えるでしょう。
「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」という一度聞いたら忘れられない歌詞とともに、徳島中が盛り上がる様は勇壮です。
起源に関しては諸説ありますが、400年以上の歴史があると言われています。現在でもとても活気があります。
現在主流となっている定番曲は「東京音頭」と「炭坑節」です。
盆踊りの経験がある人なら、一度は耳にしたことがある可能性が高いです。
近年では踊り手の不足から盆踊りが衰退し始めている地域もあります。
中には盆踊りの伝統を残そうとアニメの主題歌などを取り入れているところもあるそうです。
時代に合わせて変化していくのは自然かもしれませんが、本来のご先祖様などの霊を迎え送るという意味を忘れないようにしたいですね。
まとめ
盆踊りは、古来から続く島国日本の一体感が感じられる不思議な行事です。
踊っていて楽しいのにどこか切なさを感じるのは、平安時代から続いている祖先の供養に通じる意味が込められているからなのかもしれません。
踊りながらその歴史に思いをはせるのも素敵ですね。
スポンサーリンク











