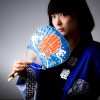亡くなられた方の四十九日が過ぎて、初めて迎えるお盆が「初盆(新盆)」です。
初盆・そして毎年のお盆には、先祖・故人を迎えて供養をします。
その供養の際に、盆提灯が飾られますが、どんな意味があるのかご存知ですか?
初盆を迎えるにあたって、初めて盆提灯というものを知ったという方もいるかもしれませんね。
せっかくの供養ですから、意味合いを知った上で飾るとより良い供養となるでしょう。
この機会に盆提灯の意味や誰が贈るものなのか・お返しは必要なのかといった、盆提灯に関する疑問について解説したいと思いますので、この機会に覚えてみてください。
盆提灯には、どういう意味がある?
お盆は、先祖・故人の霊がまずお墓に帰ってくるといわれていますが、そのお墓に戻った霊を自宅に迎える為に盆提灯は飾られます。
お墓に戻った先祖・故人の霊が、迷うことなく帰ってこられるように目印として盆提灯を飾るという意味があります。
また、お盆の供養として感謝の気持ちを表すという意味もあります。
初盆には、初めて先祖が帰ってくるので目印の意味合いと共に、清浄無垢な気持ちでお迎えするといった意味のある白提灯を飾ります。
※白提灯を飾るのは初盆だけ
本来、「迎え火」「送り火」といい、火を焚いて先祖・故人の霊を迎えていたのですが、江戸時代頃より、提灯に火を灯す形へと移り変わりを見せました。
現在も、迎え火・送り火を焚いているご家庭もありますが、住宅事情などにより盆提灯が主流となりつつあります。
また現在では、火事の危険性を考慮し、電気灯を灯したり・灯りを入れない傾向にあります。
盆提灯は、贈られた数が多いほど故人が慕われていた証になるともいわれます。
故人に対し、感謝の気持ちを伝えるものでもあり、最高のお供えものといわれているほどなので、大切なものと考えましょう。
盆提灯は誰が買うもの?
基本的に、毎年のお盆に飾られる絵柄の入った盆提灯は故人と関係が近かった方(兄弟や親戚といった近親者)が贈ります。
初盆用の白提灯に関しては、故人の身内が用意することになります。
基本はこのようになりますが、とくに決まりがあるわけではありません。
基本は上記でお知らせしたとおりですが、昨今の住宅事情もあり飾るスペースがない場合もあります。
その為、盆提灯を贈る替わりに「御提灯料」として現金を包み、ご家族がその御提灯料をもとに用意することも増えています。
どちらが良いか迷われた際は、他の親戚の方に相談するようにして決めるとよいでしょう。
盆提灯の相場はいくらくらい?
盆提灯を贈る場合は、値段より気持ちを優先することが大事です。あまり値段に拘らなくてよいでしょう。
吊るすタイプ・置くタイプとの2種類があり、素材などによって値段が違ってきます。
安いもので5千円以下のものありますし、10万円を超える盆提灯までありますので、故人との関係と、ご自身の予算を考慮した上で選ぶと良いでしょう。
*御提灯料としてお金を包む場合
故人との関係により、御提灯料の相場は違ってきます。
近い親戚:1万円~2万円
親戚 :5千円~1万円
知人 :3~5千円
※表書きは「御提灯料」と書きましょう。
〇〇代というのは、商品やサービスの代価という意味合いがあり、失礼に当たりますので気を付けて下さい。
基本的に、「御仏前」とは別に用意することになっています。
他の親族の方に、相談してみるとよいでしょう。
あまりに高価な盆提灯や御提灯料は、喪主のご家族に気を遣わせてしまいます。
ご自身のお気持ちも大事ですが、喪主のご家族に気を遣わせないように配慮することが必要ですので、高額の盆提灯や御提灯料を贈るのは避けたほうがよいでしょう。
盆提灯のお返しは必要か?
盆提灯は、お気持ちとしていただくものなので基本的にお返しは不要です。
お越しいただいた際に、料理でおもてなしするなど贈り主の方へ礼を尽くすことがお返しの替わりとなります。
また先方に不幸があった際に、盆提灯を贈ることでもお返しの気持ちを伝えられるでしょう。
しかし、何もしないことに気が引ける場合もありますよね?
その場合、返礼品(引き物)としてタオルなど用意しておいてもよいですね。
基本的には、必要ないですが贈っていただいたお相手との関係性も考慮して臨機応変に考えましょう。
まとめ
盆提灯の意味合いや疑問点について、ご紹介しましたがいかがでしたか?
盆提灯には、先祖や故人が迷わないように帰ってこられるようにする為の目印であったり、感謝の気持ちを表すものでもあります。
せっかくの供養ですから、こういった意味合いを知った上で供養するとよいでしょう。
贈る際も、感謝の気持ちを意味すると知った上でお贈りしてほしいですね。
あくまでお気持ちなので、盆提灯に対するお返しは不要ですが、贈られた方と故人との関係性を踏まえた上で簡単な引き物を用意するのもよいでしょう。
地域によって、多少違いが見られますので、参列されるご親戚に相談するとより安心です。
知らないまま恥をかいたり、誤解を招くことのないように常識として覚えておきましょう。
スポンサーリンク