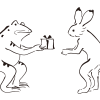美しい月を見て思わずパシャリ!
でも思ったように映らずガッカリ……
そんな経験をしたことはありませんか?
月の撮影方法にはコツがあります。
今回は月の動きを撮る方法と合わせて、徹底的に解説してみました。
見るだけでは物足りない、もう一歩踏み込んで月の魅力を知りたいという方は必見ですよ!
月の撮影方法とは?月の動きを撮ると合わせて紹介

月は身近な天体ですが、撮影するとなると初心者には少々難しいと言えます。
比較的簡単な方法から順番にご紹介しましょう。
iPhoneを使う

一番簡単な方法は、iPhoneで撮影するやり方です。
標準のカメラ機能だけでは不十分ですので
夜間撮影ができるカメラアプリを活用しましょう。
露出とフォーカスを別々にできる機能があるものを選ぶことがポイントです。
最初に室内のシーリングライトなどを使い露出にロックをかけて撮影します。
高性能なアプリでも月を撮影するとかなり小さくしか撮れませんので
最大限ズームしましょう。
双眼鏡を活用すると、さらに詳細な写真を撮ることができます。
双眼鏡で月にピントを合わせ、iPhoneで双眼鏡を覗くようにして撮影する方法です。
ただし、かなり手元がブレやすいので、綺麗な写真を撮るのは一苦労と言えます。
道具が揃えられなかったり、まずは気軽に挑戦してみたいと思う方は
iPhone撮影からチャレンジしてみると良いでしょう。
月の撮影は難しいですので、最初は思ったように撮れないかもしれませんが
気に入った写真が撮れた時の喜びはひとしおです。
望遠レンズを使う

月の撮影でポピュラーなのは望遠レンズを活用する方法と言えます。
これがあれば比較的簡単に美しい月の写真を撮ることが可能です。
三脚はあれば便利ですが、手持ちでも十分に撮影できます。
まず、200mm以上の望遠レンズを用意します。
カメラをマニュアルモードにして露出を設定しましょう。
ISOを100〜400にしてF値はF8くらいにします。
シャッタースピードに関しては、自分で試しながら最適のポイントを探してみましょう。
ちなみに月の写る大きさは「焦点距離✕0.01」です。
焦点距離が200mmなら200✕0.01=2mmとなります。
トリミングすると、自分の望むような大きな月の写真に仕上げることが可能です。
最初は満月を撮影することがオススメと言えます。
様々な形に変化する月の中でも、綺麗に撮れやすいです。
月を撮影するポイント

月を撮影したい時は、事前準備も大切です。
夜間の撮影になりますので早めに撮影ポイントに行って
ロケハンをしておくと安心感が増します。
昼間と夜とでは、見え方が違います。
昼間は良さそうに見えても、夜になると邪魔になるものなどもありますので
夜間撮影であることを考慮して場所を選ぶことが大切です。
夜をイメージしテスト撮影をしてみるとわかりやすいでしょう。
光害情報、当日の天候、月齢は事前に調べておきます。
日の入りや月の出と入りを把握しておくことも必要です。
季節に合わせた防寒対策も済ませておくと良いでしょう。
もし、初めての撮影で不安がある時は、慣れている人に
同行してもらう方法も有効と言えます。
夜間撮影のポイントを無駄なく理解できるでしょう。
月の動きを撮りたいならインターバル撮影
月も太陽と同じで動いて見えます。
月の軌道を連続的に撮りたいなら、インターバル撮影機能を活用しましょう。
インターバル撮影とは、設定した時間ごとに連続的に写真を撮れる機能のことです。
カメラに付いていない場合はタイマーレリーズを使えば撮影可能になります。
インターバル撮影には三脚が必須です。
また、フォーカスをロックしておくことがコツと言えます。
インターバル撮影の場合は、必ずしも対象がセンターにある訳ではないので
オートフォーカスだとぼやけてしまう可能性があります。
レンズは構図によって変わってくるので、色々試してみると良いでしょう。
撮影ポイントに三脚とカメラを設置したら、月にピントを合わせてインターバル撮影します。
出来上がった写真を見ると月の動きがよくわかるでしょう。
一番の注意点は、撮影中にカメラが動かないようにすることです。
うっかりズレてしまうと、ブレが発生し綺麗に撮れません。
三脚は安定感のあるものを選び、足場もしっかりした所にすることがコツと言えます。
月の撮影の魅力は月の動きを撮ることだけではない?

月の魅力は、何と言っても様々な表情を見せてくれることです。
満月だけでなく、三日月、上弦の月、下弦の月など、満ち欠けが作る姿は多彩です。
満月を撮ることに慣れたら、ぜひ色々な月齢の月にチャレンジしてみてください。
新たな月の素晴らしさを知ることができます。
こちらでは、面白いシュチュエーションの例をご紹介します。
月の満ち欠けを味わう

月齢によって月の表情は変化します。
夕焼け空に浮かぶ三日月など、他の月齢の時とは一味違うシャッターチャンスも豊富です。
満月に慣れたら、月の形の変化を楽しむようにしてみてはいかがでしょうか。
作品の幅も広がります。
星と組み合わせる

星々と組み合わせて月を撮るのも良いでしょう。
四季折々の星と一緒に撮ったり、天の川を活かすなど
組み合わせ方は無限の広がりがあります。
星空写真として構図を考えることもまた違った面白さがあるのでオススメです。
風景として撮る

月を主役ではなく、風景の一部として活かす方法も良いでしょう。
前景に人工的な建物や、木などの自然の一部が入るようにすれば
月の見せ方を工夫することができます。
対比効果も活用して月を自在に撮れるようになると、月撮影の楽しさがグッと深まります。
雲との共演を楽しむ

フォトジェニックな光景を撮りたい時は、月と雲との共演を撮影してみましょう。
狙って撮れる光景とは言い難いですので、月の動向をよく観察し
見つけた時に逃さず撮影する技術が必要になります。
月傘や月光環など月と雲が織りなす幻想的な現象もシャッターチャンスです。
レアな月にチャレンジする

太陽と地球と月が一直線に並ぶことで起きる皆既日食など
神秘的でレアな月の撮影にチャレンジしてみるのも良いでしょう。
美しく撮るにはそれ相応の技術が要りますので、慣れていることも重要です。
レアな分、撮れる機会が限られています。
普段から練習しておいて、貴重な瞬間を逃さないようにしましょう。
一番大切なのは、月の撮影を楽しむ気持ちです。
プロを別にして、月の撮影は強制されているわけではありません。
月の撮影に熱心な方は、撮影そのものを楽しんでいます。
思いがけず良い写真が撮れる日もあれば、出来たと思ったのに
上手く仕上がらず残念な日もあるでしょう。
その全てが経験となります。
月やカメラ、気候条件などの詳しくなれば、どんどん技術は向上していきます。
あなたならではの月の写真が撮れるように、楽しみながら積極的に撮影してみましょう。
月の撮影には月の動きなどを理解しておくことが大切

美しい写真撮影には、カメラの機能を理解すると同時に
被写体への知識を深めておこうことがポイントとなります。
月の撮影に挑みたいなら、月そのものへの理解を深めましょう。
本などから知識を吸収する方法も有効ですが、実際に観察してみることも肝要です。
自宅で構わないので、毎日同じ方向、同じ場所
同じ時間で月の動きを観察してみましょう。
1ヶ月位すると、月の動きを把握できるようになります。
もちろん季節などによって見え方は異なってきますが
1月観察した結果がわかっていると、新しい状況でも短時間で理解しやすくなります。
ちなみに、月は東から登って西に沈みます。
見る方向を工夫すれば、昇る月や沈む月などを観察しやすくなります。
いきなり細かい条件を考えすぎると疲れてしまいますので
興味を覚えたら出来ることからはじめてみましょう。
どうすればベストな写真が撮れるのか、撮りながらチェックすることも効果的です。
シャッター速度を変えてみたり、色を調整したりして
自分の望む写真に仕上げるベストなポイントを探ってみましょう。
人の作品を見て、工夫の仕方などを学ぶこともできます。
現代ではSNSが発達していますので、カメラが好きな人の作品を
気軽に見て楽しむことができます。
プロの作品も勉強になりますが、あまりにレベルが違いすぎると
モチベーションが低下してしまうこともあるでしょう。
まずは気楽に見れる人の作品から参考にしてみる方法も有効です。
月の撮影は自分でなくてもOK?月の動きのフリー素材もある
自分で写真を撮ることにはあまり興味がないけれど
魅力的な写真が欲しいと思ったらフリー素材を活用して見ると良いでしょう。
日本だけでなく、海外の人の作品を無料で入手できるサイトも豊富です。
最近では、フリー素材と言えどもどんどんレベルが高くなっており
多種多様な月の写真を入手することが可能です。
月の動きがよくわかるインターバル撮影の写真も
フリー素材で手に入れることができます。
子どもに說明する時にも、使い勝手が良いでしょう。
ただし個人で楽しむ以上のことをする場合は
フリー素材と言えども注意が必要です。
フリー素材と書いてあっても細かい点をよく確認するように配慮しましょう。
フリー素材と書かれていても、著作権を完全に放棄していない場合や
条件がついていこともあります。
著作権は知らなかったでは済まされない問題ですの
正しく理解して適切な対応を1人1人が行うことが大切です。
基本的に利用規約に注意点が記載されていますので
フリー素材を活用する時は、よく読み込んで使うようにすると間違いないでしょう。
まとめ
見るだけでなく、撮影も出来るようになると、さらに月に対して興味が尽きなくなります。
興味を覚えたら、自分にできそうなことから試してみましょう。
徐々に出来ることが増えてくるとより楽しくなります。
スポンサーリンク