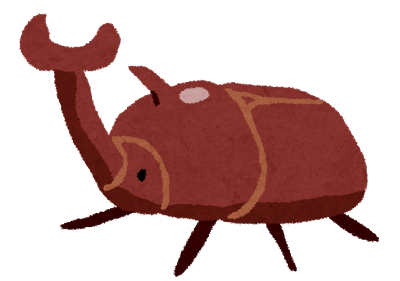昆虫採集の定番カブトムシ。
とるだけで満足という方もいるでしょうが、育ててみることもおすすめできます。
しかし、いざ飼育しようとしても、方法がわからず困惑したことはありませんか?
小さな命を育てるためには、何点かポイントがあります。今回は、初めてカブトムシを飼育する方向けに、情報をまとめてみました。
おすすめのエサや寿命など、カブトムシに関するあれこれを一挙にご紹介します。
これを読めば、初心者の方でもバッチリカブトムシを飼育できますよ。
カブトムシは誰でも飼育できる!
カブトムシを育てるのは、意外と簡単です。
その為、子どもが始めて飼う生き物としてもおすすめすることができます。
まずは、カブトムシを捕まえることからチャレンジしてみましょう。
現代では購入することもできますが、カブトムシ採集からスタートすると、愛着がわき、より親しみを持って育てることができます。
また、飼育を始める前に家族の了解はとっておきましょう。
特に女性の中には、カブトムシなどの昆虫が苦手という方もいますので、ママの許可をとってから飼育を始めることが大切です。
パパに味方してもらうと、説得しやすいかもしれません。
飼育準備に必要なもの
カブトムシを手に入れ家族の許可がおりたら、必要なものを用意しましょう。基本的に以下の3つが必要です。
1飼育ケース
2昆虫マット(土)
3葉っぱ・止まり木
どれもホームセンターで簡単に入手することが可能です。手順と合わせて詳しく見ていきましょう。
1飼育ケース
飼育ケースは産卵まで考えるなら大きい方が良いでしょう。
1つがいなら20cm×10cmくらい、オス2匹にメスが3~4匹くらいなら40cm×20cmくらいの大きさが必要です。
メスが多いほうが産卵の可能性が高まります。
また、メスの数が少ないとオス同士がエサとメスを取り合ってケンカしてしまい早死することがあるので注意しましょう。
2昆虫マット(土)
飼育ケースを用意したら、昆虫マットを入れます。
昆虫マットとは、昆虫飼育用品です。
産卵まで考えるなら「成虫飼育用」ではなく「腐葉土タイプ」を選ぶようにしましょう。
カブトムシの幼虫は腐葉土を食べて成長します。
腐葉土は厳密には土ではなく、自然界で多くの微生物や枯葉などの有機物が分解されてできたものです。
これを人口で作るのは容易ではありません。
そこで、飼育用に昆虫マットが開発されています。幼虫は、このマットを棲家としながら、同時に食料にして大きくなるのです。
手軽に購入できますが、種類が豊富ですので、育てたいカブトムシに適した昆虫マットを選んであげましょう。
3葉っぱ・止まり木
昆虫マットを入れたら、葉っぱ・止まり木となる枯れ木を敷いてあげましょう。
100円ショップ購入する方法もありますが、公園などで落ちているものを入れれば無料です。
なぜ敷くかというと、カブトムシはひっくり返ってしまうと高確率で戻れなくなります。
そのままにしておくとあがいている内に疲れて死んでしまいます。
そこで、ひっくり返っても捕まって戻れるように葉っぱなどを敷いてあげるのです。
これでカブトムシの棲家は用意することができました。
いよいよ飼育に入っていきます。
カブトムシの飼育の1年間スケジュール
細かい解説の前に、カブトムシを育てる上での1年間のスケジュールを把握しておきましょう。
まず夏はカブトムシ採集と交尾をさせる時期です。
産卵を経て続いて秋からは、幼虫飼育がスタートします。
寒くなる前に容器内のマットをかえ糞がたまらないように配慮します。
冬は冬眠期間です。
春になったら再びマットをかえ、蛹になるまで見守ります。
そして夏になると成虫になって土の上にでてきます。
カブトムシは成虫になってから冬を越せることはほぼありません。
これが1年のスケジュールになります。続いて、細かい飼育方法を確認していきましょう。
カブトムシの飼育方法~産卵から幼虫まで~
昆虫マットと葉っぱなどを入れたケースを風通しの良い日陰に置きます。
温度帯は20~28℃くらいがベストです。
そしてつがいのカブトムシを入れます。
乾燥には注意が必要です。
マットが乾燥してきたら霧吹きを活用して適度に湿り気を加えてあげましょう。
まずはエサを与えてあげます。
100円ショップで売られている昆虫ゼリーで十分です。
昔は食べ終わったスイカやメロンの皮を与えている人もいましたが、実は水分の多いエサはカブトムシのオシッコの量が増えてしまい、飼育ケース内が不衛生になりやすいのでNGです。
コバエも湧きやすくなってしまうので気をつけましょう。
カブトムシは盛んに交尾をします。
メスが地中に潜って出てこなくなった産卵をしている証拠です。
腐葉土タイプの昆虫マットを多めにいれておけば、そのままでも育つことができますが、成虫が日中潜った時に傷つけてしまう可能性もありますので、可能なら、取り出して隔離しましょう。
採卵は直接手で触るのはおすすめできません。
細菌などがついたり、潰してしまう危険性があります。
スプーンを使いましょう。
取り出した卵は、腐葉土タイプの昆虫マットを敷いたタッパーなどに移します。
細い棒で卵を入れるための穴をあけ、卵を1つずついれてあげます。
上からマットをかけ、通気を確保した蓋をして、4~8週間くらいおくと孵化して幼虫になります。
幼虫になったら、成虫とは別の飼育ケースに移します。
カブトムシの飼育方法~幼虫から成虫まで~
カブトムシは一生の間をほとんど幼虫として過ごします。
その期間は約10ヶ月程度です。
複数飼育もできますが基本的には1つのケースに1匹ずつ育てる方法が無難でしょう。
カブトムシは放っておくとじゃんじゃん交尾をして、どんどん産卵しますので、自分が育てられる範囲に調整するように気を配っておくと良いでしょう。
多く採取しすぎたなら自然に返すという方法もあります。
幼虫飼育におけるポイントは「マットの交換」と「適度な水分」の2つです。
幼虫はとにかくよく食べ、同時に大量の糞をします。
放っておくとケース内が糞だらけになってしまうので、衛生を保つためにもマットの交換を行いましょう。
最低でも秋と春の2回は行う必要があります。
冬の間は冬眠していますので、寒くなる前にマットを一度交換してあげることが大切です。
換え時の目安は、マットのかさが減ったり、糞が目だってきた頃行うようにすると良いでしょう。
実は成虫になってから体が大きくなることはありません。
幼虫の時にどれだけ食べたかによって体の大きさが決まります。
その為旺盛な食欲があります。
始めて育てる時は驚くかもしれません。
生命の不思議を学べるチャンスと言えます。
乾燥させすぎと水のやり過ぎは注意が必要です。
適度な水分を保てるように霧吹きなどで随時湿らせてあげましょう。
蛹になったあとは、衝撃に弱いので注意しましょう。
下手に衝撃を与えてしまうと奇形になったり死んでしまうので気を配ってあげることが肝要です。
蛹になってから4~8週間ほどで 羽化し、成虫になります。
羽化した後はしばらくデリケートです。
傷つけあわないように1頭ずつ個別に飼育してあげましょう。
また、気になってもあまり触らないようにすることも大切です。
羽化してもすぐにはエサを食べませんが、いつ食べ始めても大丈夫なようにケースに用意しておきます。
十分な成熟期間をおくと、成熟し交尾活動ができるようになります。
目安としては、「エサを食べるようになった」「羽ばたきをするようになった」といった行動を見せるようになれば、成熟していると判断できます。
カブトムシにとって良いエサベスト3
カブトムシにとって、良いエサは何でしょうか?
1番良いのはバナナです。
植物性タンパク質も豊富で栄養があります。
2番めに良いものが昆虫ゼリー、3番めがりんごです。
この内、一番手間がかからず人気があるのが昆虫ゼリーです。
腐りにくいのでケース内に長く入れておける他、ストックができて用意する際に果物のように切る必要もなく手軽なことから重宝されています。
昆虫ゼリーは100円ショップで売っているので、お値段的にもリーズナブルと言えるでしょう。
飼育をするなら昆虫ゼリーをエサにする方法がおすすめと言えます。
昆虫ゼリーや果物、野菜以外のエサとしては、産卵前のメスに加糖されたヨーグルトなどの動物性タンパク質が豊富なエサを与えることがあります。
水分の多いエサはNGです。
砂糖水もおすすめできませんので注意しましょう。
野外のカブトムシは、とうもろこしやトマトなども食料にしています。
カブトムシの寿命とは?
カブトムシの寿命は、12ヶ月~15ヶ月くらいです。
ただし、この内で成虫である期間は1ヶ月~3ヶ月くらいになります。
残りの10ヶ月前後を幼虫として過ごします。
どんなに丁寧に飼育しても、成虫が冬を越せないのは寿命だからです。
また、成虫になっても1ヶ月くらいは蛹室の中で待機しています。
その後、地上に出てエサが食べられるようになってから、命が燃え尽きるまでの短い期間で子孫を残すために活動するのです。
人間とは違う命のあり方を学ぶことが出来るでしょう。
カブトムシが死んでしまったらどうしたら良いでしょうか?
一般的には埋めるという方法があります。
ただし地区によっては公園などの公共の場に埋めることを禁止している場所もありますので、各自事前に確認することが大切です。
もし埋められない時は、かわいそうですが燃えるゴミとして出す方法も選択することができます。
カブトムシのオスとメスの見分け方は?
幼虫の段階でオスとメスを見分けることが可能です。
おしりから2番目の線と3番目の線の間を見てみましょう。
「-」のような横線があればオス、なければメスです。
国産カブトムシの場合は印が「v」になります。
また体重で見分ける方法もあります。
一般的にオスの方がメスよりも一回り大きく育つ傾向があります。
オスが約30g、メスは20gほどの体重になります。
ただし、育成環境や栄養具合によっても変わってきますので、こちらはあくまで目安と言えます。
幼虫の段階では慣れていないとわかりづらいでしょう。
成虫になればわかりやすくなり、角があればオス、なければメスです。
カブトムシの飼育中にコバエが発生してしまったら?
カブトムシの飼育中にコバエが発生してしまうことがあります。
原因としては土とエサが考えられます。
市販の昆虫マットを別として、山などで土を採取した時は、他の虫が混ざっている可能性があります。
また、エサとなる食べ物につられてケース内にコバエが侵入し、卵を植え付けられていることもあります。
コバエはたったの1日で卵から孵化し、約1週間~10日くらいで成虫に成長してしまいます。
一度発生すると、新しく誕生した成虫がまた卵を産み付けるなど負のスパイラルに陥りやすいです。
カブトムシそのものに害はありませんが、衛生的にも望ましくありません。
その為、コバエが発生したら対策を取る必要があります。
まず第一に卵を植え付けられている可能性がある土を取りかえましょう。また、エサを取りかえてあげることも大切です。
さらに、ケース本体とフタとの間に新聞紙などをはさみ、隙間が生まれないようにしましょう。
もっとしっかり対策したい人は、コバエ防虫シートをケースに被せる方法がおすすめです。
カブトムシの飼育ではカビにも注意が必要
適度な水分を確保するカブトムシの飼育ですが、6月など湿気の多い時期にはカビが発生してしまうこともあります。
カビを発生させないように気を配ってあげましょう。
ただし、まだ詳しい仕組みがわかっていませんが、実はカブトムシの幼虫はカビや細菌に対する免疫力がとても強いです。
なので、神経質になる必要はありません。
もし発生してしまっても、カビは基本的に取り除けば大丈夫です。
取り除いてもカビが多く発生してしまう場合はマットを交換してあげましょう。
蛹室を壊してしまった場合の対処方法
カブトムシが蛹から羽化するまでの間過ごしている部屋を蛹室と呼びます。
衝撃に弱い蛹の間、カブトムシを守ってくれている大切な場所です。
国産のカブトムシの場合は、縦に蛹室を作ることが知られています。
基本的にはカブトムシが蛹室を作りますが、万が一何らかの原因で壊してしまったり、カブトムシが作れなかった時は、人工蛹室を作ってあげる方法が効果的です。
人工蛹室とは、文字通り人の手で作った蛹室のことになります。
羽化の瞬間を自分の目で見たい人も見やすい人工蛹室を作る方法を採用しており、比較的メジャーと言えます。。
作り方はとても簡単です。
土を掘って作って上げる方法もありますし、トイレットペーパーの芯を活かす方法もあります。
後者の場合、まず容器の底に水で湿らせたテッシュペーパーを5枚程度重ねて敷きます。
その上にトイレットパーパーの芯を置けば完成です。
あとは人口蛹室に蛹を入れてあげれば、人工蛹室の中で観察することができます。
カブトムシが蛹になる合図として、幼虫が動かなくなり、体のツヤがなくなってきます。
もしかして死んでしまったのか?と不安になる方もいるでしょうが、焦りは禁物です。
しばらくすると脱皮が始まり、完全な蛹へと変わってきます。
蛹になってから3週間ほど経過すると、成虫として羽化します。
なお羽化しても、はじめの1週間~10日ぐらいは、体が固まるのを待っているので地上には出てきません。
ここでも焦らずに様子を見るようにしてあげましょう。
カブトムシの飼育は男の子の憧れ?
カブトムシは鳴き声があるわけでもありませんし、基本的に放置してしまっても問題になることは少ないので、飼育の手間がかかるわけではありません。
エサが切れないように気を配ったり、乾燥しないように時々水分をあげ、あとは要所要所でケース移動やマットの交換をしてあげるだけで済みます。
特に男の子は昆虫採集の定番としてカブトムシに憧れを持っていることが多いです。
自らとったカブトムシを1年じっくり育てることができれば、生き物に対する知的好奇心を満たしてあげることができます。
もし育てる機会があったらチャレンジしてみることもおすすめと言えるでしょう。
男の子は喜びやすいです。
卵や幼虫から育てることで愛着もわきます。
生き物を慈しむ心を育む意味でも、幼虫から成虫までの過程を見せてあげるのも良いのではないでしょうか?
まとめ
育成しやすく始めて飼う生き物におすすめのカブトムシ。
機会があったら飼育に挑戦してみてはいかがでしょうか?
生命の不思議を、子どもにじっくり見せてあげることができますよ。
ポイント抑えてあげれば、飼育は難しくありません。
最初は戸惑うことがあるかもしれませんが、慣れてくれば一度に数十匹を育成することもできます。
育てた成虫は森に返したり、興味がある人に配ると喜ばれやすいです。
スポンサーリンク