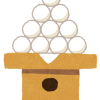1年に一度訪れる「敬老の日」。
長年社会を支えてきたご年配の方に対して
お祝いと感謝の気持ちを伝える素敵な祝日です。
気持ちを形に表す時に活用したいのがカードです。
豊富なデザインのカードが市販されていますし
手作りでオリジナルのカードを作ることもできます。
今回は敬老に日にカードを贈るコツや手作りの作り方
注意点などをまとめてみました。
敬老の日にカードを贈るコツ
敬老の日に贈って喜ばれるのがメッセージカードです。
可能ならば手書きのカードを用意するとお祝いや感謝の
気持ちが伝わりやすくなります。
カードを贈るコツとしては、以下の5つのステップを
踏まえると良いでしょう。
ステップ1:カードを贈って大丈夫かどうか確かめる
孫からおじいちゃんおばあちゃんに贈る時は
迷いなくカードを贈るだけで問題ありませんが
例えば大人が義父母に送る場合は注意が必要です。
人によっては、手紙形式以外のカードなどの手書きメッセージは
手を抜いているのではないかと不愉快に思ってしまう方もいます。
まずは、カード形式でメッセージを贈っても大丈夫かどうか
確認しておきましょう。
せっかく用意したのに無駄骨だったという事態も避けることができます。
子供からのメッセージなら、形式に拘らず喜んで貰える確率が高いです。
字にまだ自信がない幼い子供でも、一生懸命書いたメッセージカードなら
相手にとっても嬉しいプレゼントとなる可能性が高いでしょう。
ステップ2:市販品を使うか手作りするか決める
メッセージカードは多種多様な種類が販売されています。
また、インターネットで調べてみると無料でダウンロードできる
形式のカードも多いです。
市販品の場合は、デザインが完成されているので見た目にも美しく
相手の好みそうなデザインを選択できる楽しさがあります。
手作りの場合は、オリジナリティーが高く手作りならではの
あたたかみが伝わりやすいと言えるでしょう。
無料でダウンロードできる形式の場合でも、自由に工夫をすることが
可能です。
自分の行いやすいタイプはどれか、また相手の趣味や嗜好に
合っているのはどのカードかなどを考えて、決めるようにしましょう。
ステップ3:メッセージを考える
メッセージを考える時のコツは、まず「フォーマル」か
「カジュアル」かを決めることです。
カードはスペースは少ないですが、手紙よりも自由度が高い
アイテムです。
敬語や定形の挨拶を用いる「フォーマル」なメッセージにするのか
話し言葉やフランクな調子を活用した「カジュアル」なメッセージに
するのか最初に決めておきましょう。
フォーマルの場合は、「敬老の日、おめでとうございます」
「謹んで敬老の日をお祝い申し上げます」などの文章を活用します。
やや堅苦しく思えてしまうかもしれませんが
礼儀を重んじて丁寧な調子と、カードという比較的気軽に用いる
アイテムを組み合わせることでバランスが良いと言えます。
カジュアルの場合は、「また、遊びに行くね」
「敬老の日、おめでとう」など、親しい相手ならではの
文章を用います。
カードにはイラストや写真などをアレンジして活用することができます。
カジュアル形式なら、既存の型にとらわれないので工夫しがいがあります。
相手との関係性や年齢などを考慮して、「フォーマル」か
「カジュアル」かをまず決めてから文章を考えると、作りやすいです。
ステップ4:合わせて贈るものがあるか考える
大人から自分の両親や義父母に贈る場合は
カードだけだと心もとないと感じることもあります。
品物などと合わせて贈っても良いですし
外食など一緒に時間を過ごしてからカードを渡す方法もあります。
カードだけにするのか、他にも何か贈るのか
考えてから行動すると良いでしょう。
必ず何と合わせて贈らないといけないということではありません。
大切なのは長寿をお祝いする気持ちと、感謝の想いを伝えることです。
自分らしい方法を選んでみましょう。
ステップ5:贈る方法を考える
手渡しするのか、または宅急便などを使うのかなど
贈る方法を選びましょう。
遠方に住んでいる場合は、なかなか手渡しというのも
難しいかもしれません。
宅急便で贈る時も、日付指定や時間指定を活用し
敬老の日に間に合うように贈ることがコツです。
可能なら受取確認通知などを設定しておくと確実です。
敬老の日の機会に電話してみるのも良いでしょう。
離れて暮らしている人ほど、声を聞けることを嬉しいと
感じる人は多いです。
敬老の日に贈る手作りカードの作り方
敬老の日の手作りカードにもたくさんの作り方があります。
シンプルな方法としては、画用紙や折り紙などの基本台紙に
メッセージを書く方法が簡単です。
シールや写真、千代紙などでアレンジを加えると
よりオリジナリティーが増します。
孫から送る場合は、手形や足形を付ける方法もユニークで
おすすめです。
成長がわかりやすく、インパクトも大きいので印象に残りやすいです。
メッセージを書く時は、大きめの文字で見やすくハッキリ
書くことを意識しましょう。
インターネットから無料のフォーマットをダウンロードする
方法も有効です。
完成度の高いフォーマットが数多くありますので
好きなデザインを選ぶと良いでしょう。
折り紙を活用する時は、キレイな色合いの紙を貼るだけでも
仕上がりが美しくなりますが、折り鶴などを作って貼り付ける
方法もオススメです。
近年では、国際結婚をして海外で暮らしているという方も
増加傾向にあります。海外の方に贈る際に活用すると特に喜ばれます。
敬老の日にカードを贈る場合の注意点

高齢の方は、実年齢よりも自分を若いと認識しているという
統計結果があります。
だいたい10~15歳くらい若い気持ちでいる場合が多いです。
その為、年寄り扱いされることは苦手とする傾向があります。
敬老の日のお祝いだからと年齢を強調しすぎてしまうのは避けましょう。
カードに書く言葉をカジュアルにした場合は
言い回しに注意が必要です。
例えば若者言葉などを多用してしまうと、子供が他意なく使うなら
可愛げがあるかもしれませんが、せっかく貰ったメッセージの意味が
よくわからないと残念に感じてしまう方もいます。
相手に伝わりやすい言い回しを心がけるように配慮してあげると良いでしょう。
敬老の日にボイスメッセージカードもおすすめ

声を贈れる「ボイスメッセージカード」というものもあります。
「レコーディングボイスカード」とも呼ばれています。
操作方法もシンプルで、カードを開いてスイッチを押すだけで
いつでも声を聞くことができることから、このカードを喜ぶ人は多いです。
手書きのメッセージと合わせて声を贈ってみるのも良いでしょう。
もちろん、電話したり、会いに行くこともオススメです。
声を聞いたり顔を見せることがそのままプレゼントになる
場合も多々あります。
なにより一緒の時間を共有できることはお互いにとって
良い思い出となるでしょう。
敬老の日のカードに英語を加える方法も!
メッセージカードに一文だけ英文を加えるという手法もオススメです。
華やかさを添えることができます。
全文を英語にしてしまうと、相手が意味がわからず困惑してしまう
可能性がありますので、一文だけ簡単な英語を使うと良いでしょう。
例えば「おじいちゃん、おばあちゃんへ」の部分を
「To Grandpa & Grandma」としてみたり
「敬老の日おめでとう。We all love you so much!」などのように
最後に英語を加えるなどすると、カッコよく仕上がります。
ポイントは無理に難しい英文を使わないことです。
相手がちょっと調べればすぐに意味が伝わるような
言葉を選んであげると、知識欲も刺激できるのではないでしょうか。
気持ちが若返る効果も期待することができます。
学校で習いたての英語を子供が使ってくれるなどした場合は
特に喜んでくれる確率が高いと言えるでしょう。
敬老の日にカードだけでは不安?

敬老の日をお祝いした気持ちがあっても
「カードだけでは不十分だろうか?」と感じて
結局何もしないで終わってしまうという方も少なからず存在します。
一概には言えないことかもしれませんが
カードだけだからと気後れして遠慮してしまうよりも
お祝いの気持ちを行動で示す方が相手に喜んでもらえる場合が多いです。
心のこもったメッセージをカードで贈るだけでも
十分お祝いや感謝の気持ちが伝わります。
反対に思っていても行動で示さない限り相手に伝わりづらいです。
今まで特に敬老の日を祝ってこなかった場合や
対象となる年齢になって初めての敬老の日は戸惑いを
覚える方もいるでしょう。
最初は照れくさいかもしれませんが
まずは「ありがとう」「おめでとう」と言った言葉を伝えたり
カードを贈ることから始めてみると良いでしょう。
簡単なことからでも、素直な気持ちを込めると喜んでもらえます。
敬老の日にカードと合わせて動画を贈るという方法

現代は、スマホで簡単に動画を撮ることができます。
メッセージカードをと合わせて、動画などを贈る手法も効果的です。
顔が見えるということは、お互いが安心できますし
子供の成長などがつぶさにわかることから喜ばれやすいです。
カードには取っておけるという利点も存在します。
同じく動画のデータも取っておくことが可能です。
いつでも見返せるということは、贈られた側にとって
メリットがあると言えます。
新しく機能を覚えようと前向きに活動する場合もあります。
この機会に、操作を覚えることができることで
いつでも好きな時に動画を送りあえるという新しい交流方法を
作ることも出来るでしょう。検討してみるのも有効です。
まとめ
カードは、面積が少ない分、手軽に自由なアレンジを
加えることができます。
文章を考えるのが苦手な人は一言だけでもいいので
メッセージを贈ってみてはいかがでしょうか?
十分気持ちが伝わります。積極的な活用がオススメできると言えます。
スポンサーリンク