
お歳暮は日頃の感謝の気持ちを伝える贈り物です。
だからこそ、お歳暮をもらうとやはり嬉しい気持ちになるものです。
ただ、お歳暮を受け取るだけ受け取って終わりというわけにはいきません。
というのも、お歳暮を受け取ったらお礼状を送るのがマナーなのです。
特に、お客様からお歳暮を受け取った場合には今後の関係にも影響してきますので、失礼のないようにお礼状をすぐに送っておきたいものです。
ですが、お客様へのお礼状というのは具体的にどうすればいいのでしょうか?
お歳暮のお礼状はマナー!

家族や友人などの親しい間柄の相手からお歳暮を受け取った場合、お礼状というのは送らない方がほとんどかと思います。
今の時代、電話やメール、LINEでお礼を済ませてしまう方も多いでしょう。
ただ、お客様を相手では、家族や友人などと同じような対応はさすがにできません。
もともと、お歳暮への正式なお礼状というのは便箋に手書きをするのが基本です。
ちなみに、縦書きが一般的ですね。
お客様相手であれば、やはり正式なお礼状のやり方に習ったほうがいいでしょう。
ですが、あまりにもお客様からのお歳暮が多い場合には、さすがにすべてを手書きでというのは難しくなってきます。
そういうときには、無理に手書きにこだわる必要はなくて、ハガキに印刷したものを使っても問題はありません。
正式なやり方も大切ではありますが、それよりももっと重視したいのがすぐにお礼を伝えるということです。
手書きにこだわってお礼を伝えるのが遅くなってしまうよりは、印刷したものでも早くにお礼を伝えられるハガキのほうが好ましいのです。
お歳暮のお礼状というのは、思っている以上にスピーディーな対応が求められるものでもあるのです。
実際に、一度テンプレートのような形で用意しておいて、年月日のみを変えて毎年使っているというところも少なくありません。
年月日のところのみを空欄にしておいて、そこだけ手書きというケースも少なくありません。
お客様が会社の場合には?

では、実際にお歳暮のお礼状をお客様に送るとして、お客様が会社の場合にはどういう文面で送ればいいのでしょうか?
例えば、
「拝啓 初冬の候 貴社におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、このたびは結構なお品をご恵贈賜りまして、ありがとうございました。有難く拝受させていただきます。改めて、厚く御礼申し上げます。
これからさらに寒さも厳しくなってまいります。皆様どうぞご自愛くださいませ。
略儀ながら書中を持ちまして御礼申し上げます。
敬具」
といった文面であれば、問題ないでしょう。
流れとしては、拝啓で始まり、季節の挨拶、お礼の言葉、相手を気遣う言葉、締めの言葉、敬具で終わるという感じになります。
この流れに沿っていれば、OKです。
Wordなどであればビジネス文書の定型文が出てきますので、ぱっといい言葉が思いつかないときにはそういった機能に頼るのもひとつの方法です。
ちなみに、上記の例文では「貴社」という言葉を使っています。
これは相手側が会社だからこそ使う表現になりますので、逆に相手が会社以外であれば使うことはできません。
注意しておきましょう。
お客様が個人の場合には?
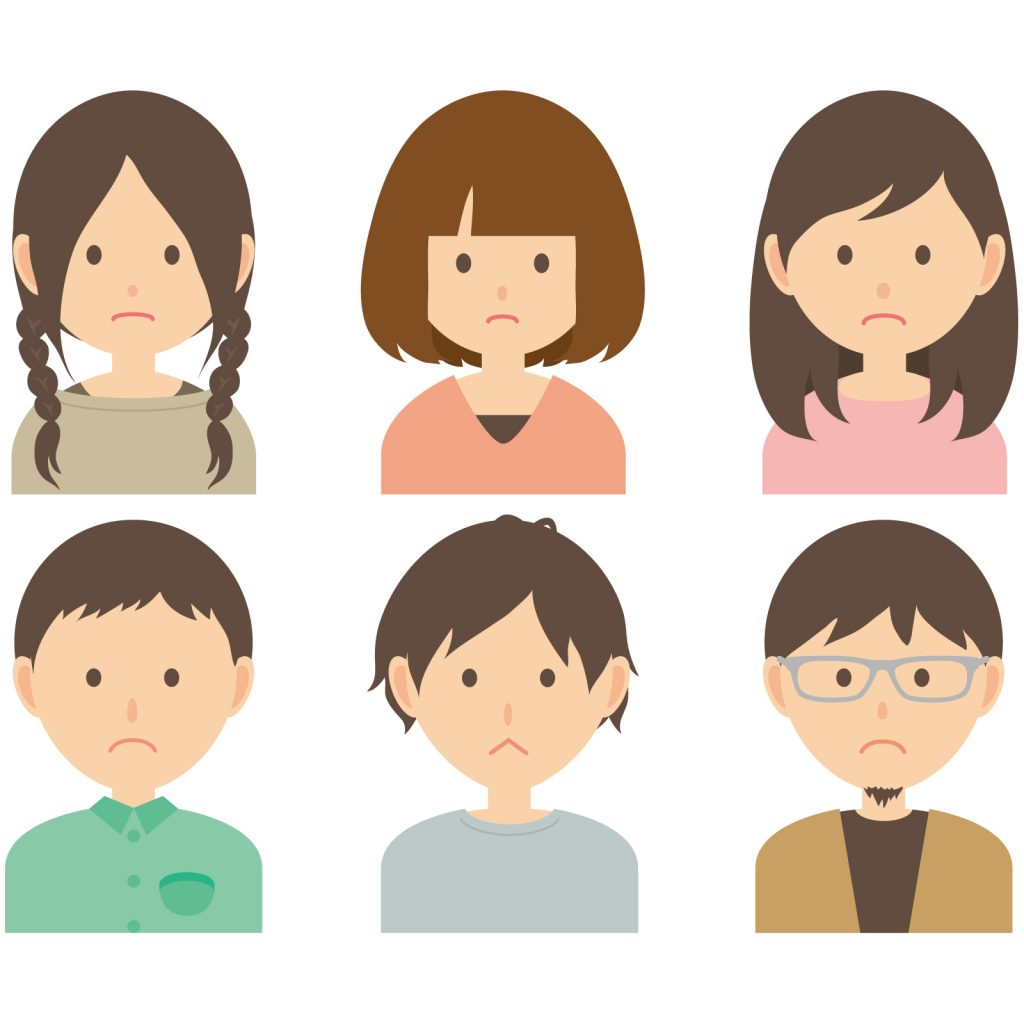
さて、先ではお客様が会社の場合の例文をご紹介しました。
会社を相手にしている場合と個人を相手にしている場合は、やはり事情が違ってきます。
ただ、基本的な流れは変わりません。
会社用の文章に少し手を加えるだけでOKです。
例えば、
「拝啓 初冬の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、このたびは結構なお品をご恵贈賜りまして、ありがとうございました。有難く拝受させていただきます。改めて、厚く御礼申し上げます。
これからさらに寒さも厳しくなってまいります。どうぞご自愛くださいませ。
略儀ながら書中を持ちまして御礼申し上げます。
敬具」
といった文面であれば、問題ないでしょう。
基本的な流れは会社を相手にしているときと変わりません。
相手が会社ではなく、個人であるということを意識した上で言葉を選べばいいだけです。
ちなみに、個人というのは事業主も含みますので、注意しておきましょう。
まとめ
お歳暮のお礼状はマナーですので、やはりお客様にはできるだけ早くに送るようにしておきましょう。
お客様が会社なのか個人なのかによって選ぶ言葉が違ってきますので、その点は注意しておきましょう。
スポンサーリンク











